
FileMakerエンジニア

人手不足、業務の属人化、複雑化する業務プロセス……。
多くの企業が「業務の非効率さ」に課題を感じている今、業務効率化はもはや一部門の課題ではなく、全社的に取り組むべき経営戦略の一つとなっています。
しかし、「何から始めればいいのか分からない」「改善のアイデアが出てこない」と悩む企業も少なくありません。
せっかくアイデアが出ても、現場で定着せずに終わってしまうケースも多くあります。
- 改善の目的や効果が現場に伝わっていない
- ツール導入が目的化し、現場の課題と乖離している
- 教育/サポートが不十分で活用されない
- 現場と管理側の温度差/意識のズレがある
本記事では、業務効率化が求められる背景から、アイデアが出ない原因、アイデアの見つけ方と活かし方、さらには実際の成功事例や定着のための具体的な工夫までを網羅的に解説します。
- なぜ業務効率化が必要とされているのか
- 業務効率化のアイデアが生まれにくい原因
- 現場から生まれるアイデアの見つけ方と活かし方
- 成功事例に学ぶ具体的な改善アプローチ
- 効果を持続させるための実践ポイント
「具体的にどうすればいいのか」を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. なぜ業務効率化のアイデアが必要なのか

業務効率化は単なる業務改善の手段ではなく、企業の存続や成長を左右する重要な課題です。
人手不足やDXの推進、競争環境の激化など、外部環境が大きく変化するなかで、従来のやり方に固執していては生産性が低下し、企業競争力が失われてしまいます。
- 人手不足と業務負荷が増加しているから
- 働き方改革やDXの流れが加速しているか初稿
- 生産性向上と競争力確保が求められているから
ここからは、なぜ今、業務効率化のアイデアが必要とされているのかを解説します。
1.1. 人手不足と業務負荷が増加しているから
多くの業界で人手不足が深刻化し、既存社員に過剰な業務が集中している現状があります。
業務効率化を行わなければ、日常業務に追われ続ける「消耗型の働き方」から抜け出すことができません。
- 採用が追いつかず、限られた人数で業務を回している
- 特定の社員に業務が偏り、属人化が進んでいる
- 残業が慢性化し、社員のモチベーションが低下している
- 忙しさから改善活動が後回しになり、悪循環に陥っている
- 業務の優先順位がつけられず、緊急対応ばかりが増えている
こうした状況を打破するには、業務のやり方自体を見直し、少ない人員でも効率的に成果を出せる仕組みを構築する必要があります。
1.2. 働き方改革やDXの流れが加速しているから
「多様で柔軟な働き方」が社会的に求められるなかで、業務効率化はその前提条件となっています。
働き方改革やDX推進の波に乗り遅れれば、人材確保や定着にも悪影響を及ぼしかねません。
- 紙や印鑑を使った非効率な業務が残っている
- テレワークに適応できず、出社前提の業務が多い
- 担当者しか分からない作業が多く、属人性が高い
- ITツールが使いこなせず、デジタル化が進まない
- 外部環境の変化に業務が追いついていない
業務を効率化してテクノロジーを活用することで、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を実現し、組織の持続可能性も高めることができます。
1.3. 生産性向上と競争力確保が求められているから
限られた人材・時間・資源でいかに付加価値を生み出せるかが、企業の競争力を左右する時代です。
業務効率化は、企業の根幹を支える土台づくりとして、最優先で取り組むべき課題です。
- 無駄な業務に時間を取られ、本来の価値創出ができていない
- 市場のスピードについていけず、ビジネスチャンスを逃している
- 業務負荷が高く、新規事業や改善活動に時間を割けない
- 顧客対応に遅れが生じ、満足度が低下している
- 他社と比較して生産性が低く、利益率が悪化している
生産性の高い組織体制をつくるためにも、今ある業務の無駄を削減し、限られた資源をより価値の高い業務に集中させる必要があります。
2. 業務効率化のアイデアが生まれにくい理由

業務効率化の重要性が広く認識されているにもかかわらず、実際には「何をどう効率化すればいいか分からない」「アイデアが浮かばない」と悩む現場も多くあります。
その背景には、組織構造や日常業務の中に潜む見えにくい障壁の存在があります。
- 業務が属人化している
- ツールやシステムが乱立している
- 問題が可視化されていない
- ITリテラシーに差がある
- 日々の業務に追われて後回しになっている
ここでは、業務効率化のアイデアが出にくい主な要因と、それが引き起こす弊害について整理します。
2.1. 業務が属人化している
特定の担当者しか業務の全容を把握していない「属人化」は、効率化の大きな妨げです。
業務がブラックボックス化していると、他の人が改善点を把握できず、アイデアを出すことも難しくなります。
- 担当者の不在や退職により業務がストップする
- 業務内容が文書化されておらず、他者が引き継げない
- 改善点の指摘や検討が「その人にしか分からない」ために進まない
- 他部門との連携が取りづらく、ボトルネックになりやすい
- 新人教育が非効率で、戦力化に時間がかかる
2.2. ツールやシステムが乱立している
業務の効率化を目的に導入したはずのツールが、かえって混乱を招いているケースも少なくありません。
部門ごとに異なるツールや独自運用がなされていると、情報が分断され、業務全体の可視性が損なわれます。
- 同じ情報を複数のシステムに二重入力しなければならない
- 情報の所在が不明確で、探すのに時間がかかる
- ツールごとの使い方や操作ルールが統一されていない
- データの連携が取れず、分析や報告に支障が出る
- ツール管理が煩雑化し、運用コストが増大する
2.3. 問題が可視化されていない
業務上の非効率は感覚的に理解されていても、定量的・構造的に可視化されていないケースがほとんどです。
どこに無駄があるのか、どの業務がボトルネックなのかが見えなければ、具体的な改善策を立てるのは困難です。
- 問題の「原因」と「結果」が切り分けられず、対処が後手に回る
- 現場とマネジメントの間で認識にズレが生じる
- 改善すべき業務の優先順位がつけられない
- データがなく「何となく非効率」という曖昧な判断になる
- 定期的な見直しや評価の仕組みが定着しない
2.4. ITリテラシーに差がある
ITリテラシーに差があると、導入したITツールを使いこなせずにアナログ作業に逆戻りするリスクが高まります。
そのため、ITツールの導入による業務改善が議論の俎上に載らなくなる場合があります。
- ITツールが導入されず、アナログ作業が残り続ける
- ITリテラシーの高い社員に業務が偏る
- 誤操作や入力ミスによるトラブルが発生しやすい
- ITスキルの習熟度の違いにより、作業スピードに影響する
- 不慣れな社員へのサポート対応が他業務を圧迫する
2.5. 日々の業務に追われて後回しになっている
改善の必要性は分かっていても、忙しい現場では「今を回すこと」が最優先となり、効率化のアイデア出しや施策検討が後回しにされがちです。
その結果、根本的な改善に取り組めないまま、非効率な状態が固定化されてしまいます。
- 慢性的な業務過多が続き、余裕がなくなる
- 改善に必要な時間や人手を確保できない
- 「改善活動=余計な仕事」と認識されてしまう
- 結果として属人化や非効率が放置される
- 「変化を嫌う文化」が定着し、成長が停滞する
3. 業務効率化のアイデアと具体例

業務効率化を進めるには、「何を・どう変えるか」という具体的なアプローチが欠かせません。
すべての業務を一度に改革するのではなく、小さな改善を積み重ねながら、自社に合った方法を模索することが重要です。
- ペーパーレス化
- システムによる一元管理
- 定型業務の自動化
- クラウドツールの活用
- 業務フローの見直しと標準化
ここでは、さまざまな業種・職種に共通して取り組みやすい代表的な業務効率化のアイデアを紹介します。
それぞれの背景や狙い、実践方法のヒントも見ていきましょう。
3.1. ペーパーレス化
紙での申請、書類回覧、ファイリング作業などは、多くの時間と手間を要する非効率な業務です。
書類の紛失や検索性の低さ、保管スペースの確保など、紙媒体の運用にはさまざまな課題があります。
- 契約書や申請書を電子化し、クラウドストレージで一元管理
- 電子印鑑やワークフローシステムを導入し、社内承認をペーパーレス化
- タブレットやモバイル端末での閲覧/回覧を推進
ペーパーレス化は、情報共有スピードの向上や業務ミスの削減、保管コストの削減にもつながります。
3.2. システムによる一元管理
部署ごとにバラバラなシステムを利用していると、情報連携に齟齬が生まれ、無駄な確認や重複作業が発生します。
一元管理システムを導入することで、業務の流れを一貫性のあるものに整えることができます。
- 顧客情報/在庫.受注/請求などの情報を一つの基幹システムに集約
- 社内業務を統合管理するERPやSaaS型の業務アプリを導入
- ダッシュボード化で情報をリアルタイムに可視化
部署間の連携強化と業務スピード向上が期待でき、経営判断の迅速化にもつながります。
3.3. 定型業務の自動化
毎日決まった処理を繰り返す業務は、自動化によって大幅な工数削減が可能です。
特に単純作業やルールベースの処理は、RPAやマクロで自動化しやすい分野と言えるでしょう。
- 勤怠集計/交通費精算/請求書作成などをRPAで自動化
- Excelのマクロを使ってデータの集計や書式変換を自動処理
- Webフォームの入力内容を自動で社内システムに連携
手作業ミスの減少と、空いた時間をより創造的な業務に充てられるメリットがあります。
3.4. クラウドツールの活用
クラウドベースの業務支援ツールは、導入のしやすさと柔軟性の高さが魅力です。
また、初期投資が少なく、場所やデバイスを問わずアクセスできるため、テレワークやフレックス勤務との相性も良好です。
ファイル共有、コミュニケーション、タスク管理など、多用途に対応できるため、業務全体の連携とスピードを向上させる効果があります。
- ドキュメントや表計算ファイルなどをクラウド上で管理/共同編集
- タスク管理/進捗管理を専用のクラウドサービスで一元化
- チャット型ツールを活用して迅速なコミュニケーションと履歴共有を実現
リアルタイム性やモバイル対応に優れており、従業員の働き方の自由度を高めながら、組織全体の生産性を底上げすることが可能です。
3.5. 業務フローの見直しと標準化
業務効率化の本質は「ムダの排除」です。
工程を見直して手順を整理し、属人化を解消して標準化を図ることが、持続的な効率化につながります。
- 現状フローを業務フローチャートで「見える化」する
- 重複業務やボトルネックを洗い出して廃止/統合/自動化
- 作業マニュアルを整備し、誰でも同じ手順で対応できる体制を整備
属人性の排除と再現性の確保により、業務の質が安定し、教育・引継ぎの効率も大きく向上します。
4. 業務効率化のアイデアを集める方法
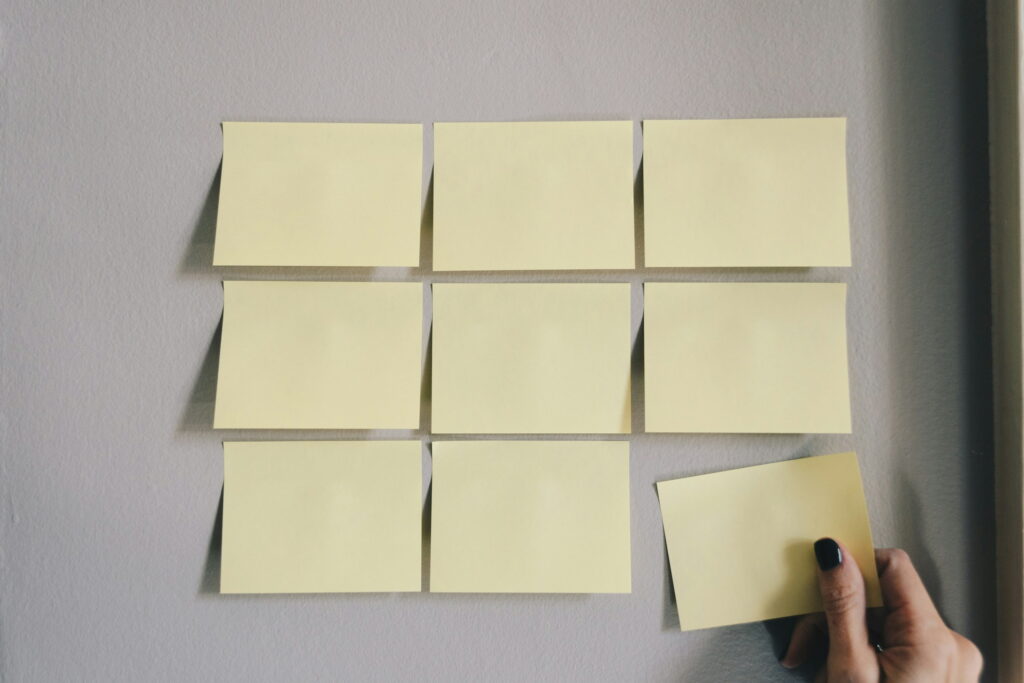
業務効率化を実現するには、まず「どの業務を、どう変えるか」のアイデアが必要です。
しかし、いざ考えようとしても現場ではなかなか良い案が出てこないという声も多く聞かれます。
- 業務日報や作業記録からヒントを得る
- アンケートで現場の声を集める
- 他社事例や業界トレンドを参考にする
- 専門家に相談する
ここでは、アイデアをゼロからひねり出すのではなく、既存の業務や他社の取り組みから「ヒントを見つける」ための具体的な方法を紹介します。
現場からのボトムアップの声と外部視点の両輪で、着実な改善につなげましょう。
4.1. 業務日報や作業記録からヒントを得る
社員が日々つけている業務日報や作業記録は、改善のヒントが詰まった宝の山です。
「どの作業に時間がかかっているのか」「同じ業務を何度もしているか」など、実態を把握することができます。
- タイムスタディ分析で作業時間の多い工程を特定
- 頻繁に発生するトラブルや遅延原因を集計
現場の当たり前を客観的に見直すことで、見落としていた課題が浮き彫りになります。
4.2. アンケートで現場の声を集める
業務効率化を考えるうえで、現場の声は何よりも重要です。
トップダウンではなく、ボトムアップ型のアイデア収集が、現実的かつ実行可能な改善につながります。
- 「困っていること」「非効率に感じること」などを自由記述で聞く
- 匿名アンケートで本音を引き出す
- 部署横断でアイデアを出し合うワークショップの開催
現場の意見はリアリティがあり、改善施策の納得度と実行力が高まります。
4.3. 他社事例や業界トレンドを参考にする
自社だけで考えていると、どうしても視野が狭くなりがちです。
他社の取り組みや業界の最新動向を知ることで、新たなアイデアや発想が得られます。
業務改善は他社から真似することが成長の第一歩です。
- 業界メディア/専門誌
- 展示会/セミナー/ウェビナー
- 成功事例紹介ページ
外部の成功事例をヒントに、自社に取り入れられるポイントを見つけましょう。
4.4. 専門家に相談する
業務改善やDX推進に詳しい外部パートナーに相談することで、自社では気づけない改善ポイントや適切なツールの選定、プロセス設計の提案を受けることができます。
特に社内にリソースやノウハウが不足している場合は、専門家のサポートが大きな助けになります。
- システム開発会社
- 業務コンサルタント
- DX支援事業者
第三者の視点を取り入れることで、偏った発想から抜け出し、より実効性の高い改善施策につなげることができます。
5. 業務効率化のアイデアを活かした事例

改善のプロセスやポイントを具体的に把握することで、自社に応用できるヒントが見つかるはずです。
- アナログ管理からクラウド移行
- 属人化した作業のシステム化
- ワークフローの再構築
ここでは、実際に業務効率化のアイデアを実現し、大きな成果を上げた企業の事例を紹介します。
5.1. アナログ管理からクラウド移行
「紙とExcelによる管理」に限界を感じていた企業が、クラウドへの移行によって大きな改善を果たした事例です。
属人化と手作業による非効率をどう解消したのかを紹介します。
| 課題 | 製造業A社では、在庫管理を紙の帳簿とExcelで行っており、リアルタイムの在庫把握が困難。 業務が属人化していたため、担当者の不在時には確認が滞り、誤出荷や棚卸ミスも頻発していた。 |
| 解決策 | クラウド型の在庫管理システムを導入し、入出庫記録や在庫数をリアルタイムで一元管理できるようにした。 バーコードリーダーやモバイル端末との連携により、現場でも簡単に入力・確認が可能になった。 |
| 成果 |
|
小さな部署単位からの導入→社内全体への展開というスモールスタート方式が、抵抗感なく定着につながった好例です。
5.2. 属人化した作業のシステム化
長年の経験と個人の判断に頼っていた業務を、システムによって標準化・共有化した事例です。
現場の混乱を最小限に抑えながら、作業の属人化を解消しています。
| 課題 | 建設業B社では、日報や工事進捗管理をベテラン社員の紙メモと電話で行っており、情報の集約や伝達に大きな手間がかかることが課題。 経験値に依存した運用のため、若手への引き継ぎも困難になっていた。 |
| 解決策 | クラウド型の現場管理アプリを導入し、スマートフォンやタブレットで日報・工程・写真などを共有可能に。 これにより、誰でも情報が把握できる環境を構築した。 |
| 成果 |
|
ITに不慣れな現場スタッフでも扱いやすいUI設計のツールを選定したことが、定着成功の鍵となりました。
5.3. ワークフローの再構築
複雑化した部門間の業務フローを根本から見直し、全体の最適化を実現した事例です。
業務そのものの設計から取り組むことで、システム導入以上の成果を上げた成功例となっています。
| 課題 | 医療機関向けサービスを提供するC社では、受注→契約→納品→アフター対応までの一連の流れが複数の部門に分かれており、業務プロセスが煩雑。 情報の引き継ぎミスや確認漏れが多く、クレームにもつながっていた。 |
| 解決策 | 部門横断的な業務フローを一から再設計し、SaaS型の業務管理システムでプロセスを一元化。 各工程のステータスをリアルタイムで共有し、担当者間の連携を強化した。 |
| 成果 |
|
システム導入だけでなく、業務フローそのものを見直したことで、根本的な非効率の解消につながった成功事例です。
なお、自社に合った改善策を見つけたい方、他社の具体的な取り組みをもっと参考にしたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。導入のヒントを得たい方や、現場への落とし込みに悩んでいる方にとって有益な情報源となるはずです。
6. 業務効率化のアイデアが活かせなくなる原因

優れたアイデアや便利なツールを導入しても、現場で「使いこなせない」「定着しない」ままでは、業務効率化の本来の効果は得られません。
効率化の取り組みがうまくいかない背景には、共通する落とし穴があります。
- 社内の合意形成が不十分だった
- ツール導入が目的化していた
- 教育やサポートが不足して形骸化した
- 多角的な視点が不足していた
ここでは、企業が陥りがちな失敗パターンとその根本原因を明らかにし、改善へのヒントを紹介します。
6.1. 社内の合意形成が不十分だった
業務効率化は、現場の協力なしには成立しません。
しかし、改善策が「上層部の一方的な指示」と受け取られてしまうと、現場は自分事として捉えられず、結果的に抵抗感を生みます。
- 目的や背景が共有されないまま「これを使って」と押し付けてしまう
- 業務実態を把握せずに改善案を決定してしまう
- 関係者への説明や巻き込みが不足している
- 改善の動機が伝わらず、「やらされ感」が生まれる
- 不満や誤解によって現場の協力が得られない
- 現場主導で運用されず、改善が形骸化する
- 現場の課題感や意見を事前に丁寧にヒアリングする
- 「なぜこの改善を行うのか」「何が変わるのか」を可視化して伝える
- 成果や進捗を定期的に共有し、全体で取り組む文化をつくる
6.2. ツール導入が目的化していた
業務効率化の手段であるはずのツール導入が、いつの間にか「導入すること」自体がゴールになってしまうケースも少なくありません。
目的と手段が逆転したまま進行すると、効果は薄れてしまうでしょう。
- 流行やベンダーの提案に流され、課題分析を飛ばして導入してしまう
- 現場の業務フローを見直さず、ツールをそのまま被せるだけになる
- KPIが導入件数や利用登録数など「形だけの数字」に偏る
- 課題とツールの機能がマッチせず、定着しない
- 運用コストだけがかかり、効果測定もできない
- 現場から「結局、前のやり方の方が楽」と言われてしまう
- 現場のボトルネックを明確化し、「何を解決したいのか」を言語化する
- 導入前に複数ツールを比較し、導入目的に最適なものを選ぶ
- ツールはあくまで業務改善の一手段であるという前提を徹底する
6.3. 教育やサポートが不足して形骸化した
どれだけ優れたシステムやプロセスを導入しても、それを正しく使える環境が整っていなければ、業務効率化は失敗します。
特に導入初期は、教育・サポート体制の充実が不可欠です。
- 操作方法を説明する時間がなく「各自で覚えて」と放置してしまう
- マニュアルが難解で、誰も読まない
- 問題が起きても相談できる窓口がない
- 使い方を誤ってトラブルが発生する
- 一部の社員しか使わなくなり、属人化が再発する
- 結局「手書き」や「Excel」に戻ってしまう
- 導入時に研修や実践形式のトレーニングを実施する
- 操作マニュアルを分かりやすく整備し、動画やQ&Aも活用する
- 導入後1~3ヶ月間は手厚くフォローし、不安を払拭する
6.4. 多角的な視点が不足していた
業務効率化は、単一部門だけの視点で進めると「他部署にしわ寄せが出る」「全体の最適化が損なわれる」といった問題が起こります。
現場レベルと全社視点を両立させた設計が必要です。
- 特定の部門だけで改善策を決定してしまう
- 他部署との連携や影響を考慮していない
- 組織全体を横断する“設計者”がいない
- 一部の業務が楽になる代わりに、別の業務が煩雑化する
- 情報が分断され、システムや業務の断絶が起こる
- 現場の混乱を招き、改善そのものが頓挫する
- 複数部門から代表者を選出し、改善プロジェクトに参加させる
- フロー全体を見渡した上で設計し、全社的な整合性を確認する
- 外部の専門家を交え、第三者視点でのアドバイスを得る
業務効率化のアイデアが成果につながらない背景には、「現場の理解不足」「手段と目的の混同」「教育・サポートの欠如」「全体最適の視点の欠如」といった共通の落とし穴があります。
これらの課題を乗り越えるには、単にアイデアを出すだけでなく、現場への丁寧な導入と、継続的に機能させるための設計と支援が不可欠です。
7. 業務効率化のアイデアを実現させる際のポイント
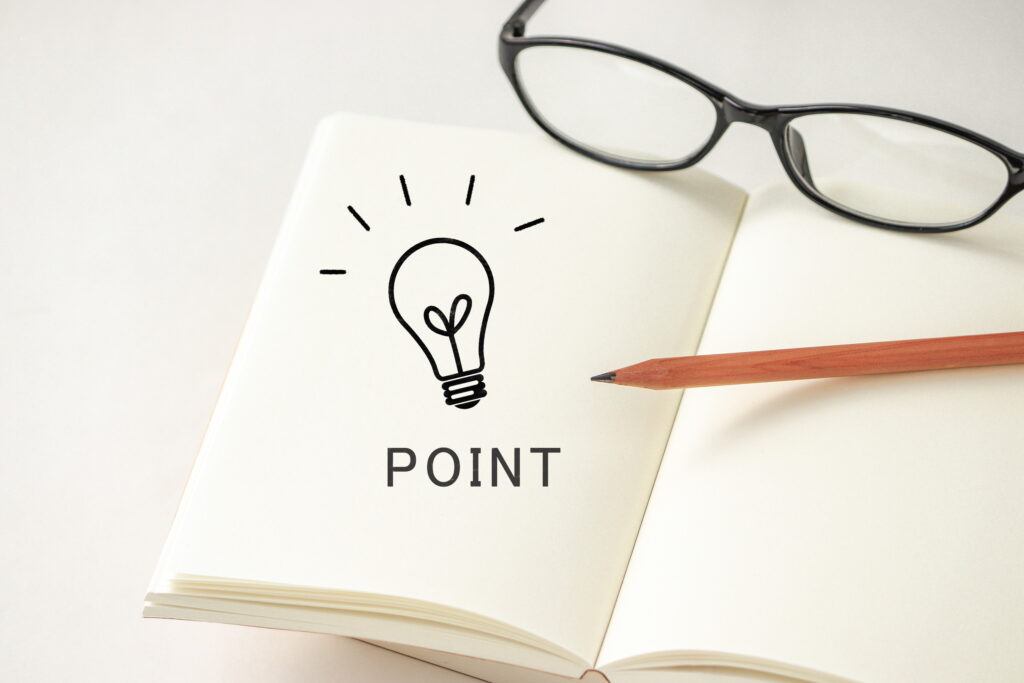
せっかく生まれたアイデアも、うまく実行に移せなければ効果は出ません。
- 現場視点での課題発見を意識する
- 小さな改善から始める
- 定量的な目標を設定する
- 効果検証とPDCAを回す仕組みをつくる
- 外部パートナーと連携する
ここでは、業務効率化を「アイデアで終わらせず」「現場に根づかせる」ための実践ポイントを紹介します。
7.1. 現場視点での課題発見を意識する
業務改善を進めるうえで、最も重要なのは「机上の空論にしないこと」です。
経営層や管理者の視点だけでなく、実際に業務を担う現場社員の視点から課題を発見することで、現実的かつ納得感のある改善が実現します。
- 作業者の動線や作業時間を観察してムダを発見
- ヒアリングやインタビューで本音の不満を引き出す
- ボトムアップでアイデアを集める仕組みをつくる
利用者の実感に根ざした課題発見は、実行可能で持続性のある業務改善につながります。
現場の声を起点にすることが、改善の第一歩です。
7.2. 小さな改善から始める
業務効率化は一気に大きく変えようとすると、失敗や混乱のリスクが高まります。
まずは「今日からできること」「すぐに効果が出やすいこと」から始め、成功体験を積み重ねることが大切です。
- Excel作業をテンプレート化して5分短縮
- 朝のミーティングを10分に短縮し、議事録はチャットで共有
- 印刷物の2割をPDF共有に切り替える
身近な業務から着手し、小さな成功を積み重ねることで、改善活動が社内に自然と定着します。
成功の実感は、次の改善のモチベーションになります。
7.3. 定量的な目標を設定する
「業務を効率化する」ことが目的化してしまうと、ゴールが曖昧になり、結局どれだけ効果があったのか分からなくなります。
成功の可視化と検証のためにも、定量的なKPI(重要業績評価指標)を設けることが重要です。
- 日報提出時間を15分以内に短縮する
- 月間残業時間を10%削減する
- 顧客対応1件あたりの時間を20分以内にする
改善の成果を数字で測定することで、進捗や効果が明確になり、全社的な巻き込みや継続的な改善にもつながります。
7.4. 効果検証とPDCAを回す仕組みをつくる
業務改善は一度やって終わりではなく、「効果を測定し、課題を見直し、さらに改善する」ことが成功の鍵です。
そのためには、PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)を組織的に回す仕組みが不可欠です。
- 月1回の改善振り返りミーティングを実施
- チームごとにKPIの進捗報告を共
- 改善アイデアを随時アップデートしてデータベース化
改善を「習慣化」するためには、PDCAを回す体制が必要です。
継続的な見直しとアップデートこそが、業務効率化の定着を生み出します。
7.5. 外部パートナーと連携する
自社だけで業務改善を進めようとすると、ノウハウ不足や人的リソースの限界に直面することも少なくありません。
そんなときは、業務効率化に精通した外部のパートナーに相談し、適切な支援を受けることが効果的です。
- 客観的な視点から課題を洗い出してもらえる
- ツール導入や設計がスムーズになる
- 現場への定着支援まで一貫して任せられる
限られた社内リソースを最大限に活かすためにも、信頼できる外部パートナーとの協働は有効です。
専門家の力を借りることで、スピードと確実性が格段に上がります。
8. 業務効率化のアイデアに悩んだらブリエ

業務効率化のために「何から始めればいいか分からない」「ツールの選定や設計が難しい」と感じているケースは少なくありません。
ブリエは、業務の見える化から業務フローの再設計、クラウドシステムやアプリ開発による効率化まで、幅広い支援実績を持つシステム開発会社です。
業務分析/改善提案
属人化・重複・非効率を洗い出し、改善余地を明確化します。最適なツールを使用したシステムの設計/開発
現場に合わせたシステム構築で、スムーズな業務移行を実現。クラウド移行支援/運用サポート
ITリテラシーが不安な企業でも、安心して業務をクラウド化できます。
業務効率化は、とりあえずツールを入るのではなく、現場に根ざした業務効率化を進めることが重要です。
業務効率化のアイデアに悩んでいる場合は、ぜひ株式会社ブリエにご相談ください。
9. まとめ
- 人手不足や業務負荷の増大に対応するため
- 働き方改革・DX推進といった社会的変化に適応するため
- 生産性を高め、企業の競争力を確保するため
- 業務が属人化しており、改善点が共有されにくい
- 課題が可視化されておらず、何を改善すべきか不明確
- ITリテラシーや導入スキルに個人差があり、取り組みが定着しない
- 日々の業務に追われ、改善活動が後回しになってしまう
- 日報や業務記録、アンケートなどから問題を可視化する
- 他社事例や業界トレンド、専門家の知見を取り入れる
- 現場視点で課題を洗い出し、小さな改善から着実に取り組む
- 成果を測定しながら、継続的にPDCAサイクルを回す
- 部署を横断した全社的な合意形成を行う
- 効果を測る定量的な目標・KPIを設定する
- 定期的な振り返りと継続的な改善体制を構築する
- 外部の支援パートナーと連携し、スピードと専門性を強化する
業務効率化は、「仕組み」で組織の働き方を変えるための強力な手段です。
アイデアが浮かばない・成果が出ないと悩んでいる方は、本記事を参考にしながら現場に根差した業務改善の第一歩を踏み出してください。

株式会社ブリエ代表取締役。Webデザイン、WordPress、Elementor、DTPデザイン、カメラマンなどを経て、FileMakerエンジニアとなる。企業の経営課題であるDX化、業務効率化、ペーパーレス化、情報の一元管理など、ビジネスニーズの変化に合わせてFileMakerで業務システムを開発し、柔軟に拡張して解決いたします。










-1024x290.png)