
FileMakerエンジニア

せっかくシステムを導入したのに、「使われない」「評価されない」といった声が現場から上がっていませんか?
社内評価が低いシステムには、導入前の業務理解不足や、導入後の運用体制の不備など、いくつもの共通点があります。
評価を高めるには、開発やシステムそのものだけでなく、「導入のしかた」や「定着させる仕組み」が重要です。
- 現場の業務フローとシステム設計のミスマッチ
- 操作性・UI/UXの配慮不足
- 現場への目的説明や情報共有の不足
- 教育体制やサポートが不十分
- トップダウンで進めた結果の反発
- 運用ルールが不明確
- 初期設定・データ移行の不備
- システム開発会社の選定ミス
本記事では、システム導入後に評価が下がってしまう原因を整理したうえで、社内に受け入れられるシステムにするための改善策や設計のポイントをわかりやすく解説します。
- 社内評価が低くなるシステムの特徴と共通点
- 評価を高める導入・設計のアプローチ
- 業務フローに沿ったシステム構築のポイント
- 成果を生む段階的な展開方法
- 信頼できる開発会社の選び方
社内から信頼され、成果を生むシステム導入を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 社内評価が低いシステム導入が引き起こす問題

システム導入が現場に受け入れられないまま運用が続くと、単に「使いにくい」という不満にとどまらず、業務全体や組織運営に大きな悪影響を及ぼします。
- システムが使われず、投資対効果が得られない
- 業務効率が改善されず、かえって負担が増え
- 現場の不満が蓄積し、離職リスクが高まる
- 社内でのDX推進が停滞する
- 他部門への波及や全社的な運用が困難になる
ここでは、システム導入後に社内評価が低い場合に発生しやすい代表的な問題を整理します。
1.1. システムが使われず、投資対効果が得られない
どれだけ高額な費用と労力をかけて導入したシステムでも、現場で使用されなければ、その効果は発揮されません。
使われないシステムは単なる「コストの塊」となり、経営層からの評価も悪化します。
- 現場が使いづらいと感じることで、手作業やExcelへ逆戻りする
- 導入費/保守費/教育費といったコストが無駄に終わる
- 「システム化=無駄」という誤った認識が社内に広がる
1.2. 業務効率が改善されず、かえって負担が増える
業務の効率化を目的に導入したはずが、現場の業務フローに合っておらず、操作が煩雑になったり、従来よりも作業工数が増えてしまったりするケースもあります。
むしろ生産性を落とす結果になりかねません。
- 情報の二重入力が発生して手間が増加する
- 画面遷移が多く、1件処理にかかる時間が増える
- マニュアル確認が頻発し、処理スピードが低下する
1.3. 現場の不満が蓄積し、離職リスクが高まる
使いづらいシステムは日々の業務にストレスを与え、現場の士気を下げます。
その不満が蓄積すると「こんな環境では働けない」と感じ、離職の引き金となることもあるでしょう。
- 操作のストレスやミスへの不安が積み重なる
- 現場の声が無視されているという心理的不信感
- 業務負担が増え、ワークライフバランスが悪化
1.4. 社内でのDX推進が停滞する
一度システム導入が失敗したと感じられると、「また使いにくいものが入ってくるのでは」といった不安を感じるようになります。
次のDX施策への抵抗感が高まり、組織全体のデジタル化が進まなくなってしまいがちです。
- 新たなツール導入時に現場が消極的になる
- 上層部の意思決定に対して疑念が強まる
- IT推進担当への信頼が失われる
1.5. 他部門への波及や全社的な運用が困難になる
導入済み部門での評価が低いと、他部門への展開も難航します。
「〇〇部門がうまくいっていないなら、うちも使いたくない」といった声が広がり、全社的な一体運用の実現が遠のきます。
- 利用率に偏りが生まれ、システム連携が機能しない
- 情報の統一管理ができず、部署間で齟齬が生じる
- 導入効果の報告や社内広報がしづらくなる
システムの社内評価が低いことは、単なる「使い勝手の問題」にとどまりません。
業務の非効率化や人材流出、組織の変革停滞といった経営リスクに直結することを心得ておきましょう。
2. 社内評価が低いシステム導入の特徴と具体例

社内評価が低いシステムには、共通する傾向や設計上の問題があります。
- 現場の業務にフィットしていない
- 操作が複雑で、直感的でない
- カスタマイズ性が低く、現場の要望に対応できない
- 教育不足で現場がついてこられない
- サポート体制が弱く、不具合が放置されがち
- 導入プロセスで現場の声が反映されていない
ここでは、現場でよく見られる失敗例や導入時の特徴を挙げながら、評価を下げる要因を明らかにしていきます。
2.1. 現場の業務にフィットしていない
導入したシステムが、現場の業務内容やフローと合っていないと、使い勝手が悪くなります。
たとえば、現場は紙での入力作業が主流なのに、システムではPC入力が前提になっている場合など、実情とシステム設計のギャップが原因で敬遠されます。
製造業の現場で、製品検査の記録を紙のチェックリストで行っていたにもかかわらず、タブレットによるデジタル入力のみを想定したシステムを導入。
作業者は手袋や汚れのある環境でタブレット操作が困難で、結局紙に書いた後で事務員が再入力する二度手間になってしまう。
2.2. 操作が複雑で、直感的でない
「クリック数が多い」「画面遷移が多い」「専門用語が多い」といった特徴のシステムでは、操作に対する心理的・実務的なハードルが高くなります。
操作に不安や不満を感じることが増えると、「システムは面倒なもの」と認識されてしまいがちです。
物流会社で新たに導入した在庫管理システムは、商品ごとに20項目以上の入力が必要で、しかも入力順が固定。
入力担当者からは「操作に時間がかかりすぎて業務が進まない」と不満が噴出し、旧来のExcel台帳に戻すケースも発生した。
2.3. カスタマイズ性が低く、現場の要望に対応できない
現場から出た改善要望に対応できず、「結局手作業で補っている」「Excelを併用している」といった状況になると、システムへの信頼は一気に低下します。
医療系施設で導入された勤怠管理システムでは、夜勤と日勤で異なるシフトルールが設定できず、現場では手計算とExcelによる補正が常態化。
「システムより紙の方がマシ」と言われる結果になった。
2.4. 教育不足で現場がついてこられない
導入時に十分な説明会やトレーニングがなければ、システムの使い方を知らないまま運用が始まり、誤操作や使いこなせない状態が続きます。
介護施設で導入した日報記録用システムでは、操作マニュアルが50ページ超で難解。
スタッフの多くがパートやシニア層で、読む時間も意欲もなく、結局1割しかログインしていない状況が続いた。
2.5. サポート体制が弱く、不具合が放置されがち
困ったときに問い合わせても返事が遅い、または対応してくれないとなると、「このシステムは信用できない」「また不具合が起きたら困る」と判断し、利用を避けるようになります。
月末の請求書出力でエラーが頻発したにもかかわらず、開発元からの回答が1週間後。
営業部門では月末処理に支障をきたし、「肝心なときに使えない」という声が多く上がった。
2.6. 導入プロセスで現場の声が反映されていない
導入を決めたのが経営層やIT部門だけで、実際の利用者である現場が置き去りにされていると、最初から反発を招きやすくなります。
「現場のため」と言いながら現場不在の導入は、評価が低くなる典型パターンです。
本部主導で導入が決定した営業支援ツール。
入力項目や業務フローが営業の実態と合わず、営業担当者からは「結局日報の手間が増えただけ」と強い反発を招き、利用率は10%以下にとどまった。
3. システム導入後の社内評価が低い原因

社内評価が低くなるシステムには、それぞれに原因がありますが、多くは導入前後の準備不足やコミュニケーションの欠如に起因しています。
- 現場の課題や業務フローと合っていない
- 操作性が悪く、使い方が直感的でない
- 導入目的やメリットが共有されていない
- 導入・展開時の教育が不十分
- サポート体制が弱い
- トップダウンで導入が決まった
ここからは、なぜ評価が低くなってしまうのか、その根本的な原因を掘り下げます。
3.1. 現場の課題や業務フローと合っていない
現場で抱える業務上の課題や実際の作業フローが十分に把握されていないままシステムが導入されると、現場とシステムの間にズレが生じます。
- ヒアリング不足により、実務で求められる機能が反映されていない
- 業務に不要な機能が多く、使い勝手が悪くなっている
- 現場が「使う理由」を見いだせず、システムが形骸化する
結果として、「本当に必要な機能がない」「使う意味がわからない」といった不満が高まり、評価の低下につながります。
3.2. 操作性が悪く、使い方が直感的でない
どれだけ機能が充実していても、操作が複雑で直感的に使えない場合、日常業務で活用されなくなります。
- メニュー構成や入力項目が分かりにくく、操作に迷う
- 用語や画面表示が専門的すぎて、現場で理解されない
- ITリテラシーの差に対応できないインターフェース設計になる
特にシステムに慣れていないスタッフにとっては、学習コストが高いと感じられ、「触りたくない」「間違えたら怖い」と敬遠されてしまいます。
3.3. 導入目的やメリットが共有されていない
システム導入の背景や目的が社内に十分伝わっていないと、現場は「何のためのシステムか」を理解できず、積極的に使おうとしません。
- 導入時に十分な説明や説明会が実施されていない
- 部門間で導入目的の認識に差がある
- 現場にとっての「使う意義」が伝わっていない
「誰のために、何のために導入されたのか」が曖昧なままでは、納得感や主体性が生まれず、単なる上からの命令として受け止められます。
3.4. 導入・展開時の教育が不十分
導入直後のタイミングで適切な研修が行われなかったり、操作マニュアルが整備されていなかったりすると、現場は正しく使いこなすことができません。
- 操作説明が口頭のみで、記録が残っていない
- 教育対象が限定的で、現場全体に浸透していない
- 継続的なフォローやQA対応が設けられていない
特に、操作に不安がある社員にとっては、「わからないから触らない」という行動が常態化しやすくなります。
3.5. サポート体制が弱い
不明点や不具合に対してすぐに相談できるサポート体制がないと、現場の不満は蓄積していきます。
- 問い合わせ窓口がなく、対応が属人的になっている
- ベンダーとの連絡経路が複雑で、対応に時間がかかる
- 問題が起きた際に現場任せになってしまう
特に初期フェーズでは「困ったときにすぐ相談できるかどうか」が利用定着の鍵となります。
3.6. トップダウンで導入が決まった
現場の意見を聞かずに、経営層やIT部門の判断だけで導入が決まると、導入そのものに対する納得感が得られず、抵抗感が生まれやすくなります。
- 利用者の業務や悩みが無視された形で導入が進む
- 意見を言う機会が与えられず、現場が疎外感を覚える
- 「やらされ感」が強く、積極的に使われなくなる
結果的に、使う側のモチベーションが低くなり、評価も下がるという悪循環に陥ります。
社内評価が低いシステムには、現場との乖離・操作性・情報共有不足・教育不足・サポート体制・トップダウン導入といった複合的な要因が絡んでいます。
どれか1つを改善するだけでは不十分であり、システムを本当に活かすには、導入前から導入後までの「現場に寄り添った全体設計」が欠かせません。
せっかく導入したシステムが形骸化することを避けるためにも、導入前にはシステム開発会社などへの相談をするようにしましょう。
なお、株式会社ブリエでは無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
4. システム導入後に社内評価が低い場合の改善方法

社内評価が低迷してしまったシステムも、適切な対策を講じれば改善の余地は大いにあります。
- 現状の課題をアンケート・ヒアリングで洗い出す
- 簡易なカスタマイズや運用改善を実施する
- 利用メリットを再提示し、再トレーニングを実施
- 成果や改善事例を社内で「見える化」する
- 現場に活用を促す推進役を立てる
- 定期的な振り返りと改善のサイクルを組み込む
ここでは、現状の課題を可視化し、現場に受け入れられる形へと転換するための具体的な改善ステップを紹介します。
4.1. 現状の課題をアンケート・ヒアリングで洗い出す
まずは、なぜ評価が低いのか、何が使いにくいのかといった現場の声を集めることが最初の一歩です。
アンケートやヒアリングを通じて実態を把握し、表面的な声だけでなく根本的な原因を分析することが重要です。
- 利用頻度や満足度を調査するアンケートを実施する
- 現場担当者との1対1ヒアリングを行う
- 不満や要望のパターンを集計・分類する
- 問題点を部門別・業務別に可視化する
4.2. 簡易なカスタマイズや運用改善を実施する
すぐにシステム全体を刷新するのではなく、画面項目の並び替えや不要機能の非表示など、小さな改善でもユーザ体験は大きく向上します。
運用ルールの見直しやマニュアルの簡素化も効果的です。
- 使用頻度の低い機能を非表示に設定する
- 入力必須項目の見直し・削減する
- 操作手順の簡略化マニュアルを配布する
- ショートカットキーやテンプレートを活用する
4.3. 利用メリットを再提示し、再トレーニングを実施
改めてシステム導入の目的やメリットを周知し、現場にとってどんな利点があるかを具体的に伝えます。
そのうえで、理解度や操作習熟度に応じた再トレーニングを行うことで、抵抗感を払拭できます。
- 導入背景と目的をわかりやすく資料化する
- 実務ベースの操作トレーニングを実施する
- 活用事例をもとに効果を具体的に紹介する
- マニュアル・動画コンテンツを整備する
4.4. 成果や改善事例を社内で「見える化」する
「どこが変わったのか」「どう便利になったのか」を数字や事例で共有することで、社内の納得感が得られやすくなります。
成功事例を展開していくことで、利用促進のきっかけにもなります。
- 作業時間の変化や効率向上を数値で報告
- 成果をグラフ・ビジュアルで社内掲示
- 成功部門の取り組み事例を展開
- 社内ニュースやメルマガで継続共有
4.5. 現場に活用を促す推進役を立てる
各部門にシステム推進担当を設け、日常的にフォローできる体制をつくると、現場での困りごとが即座に吸い上げられるようになります。
現場との距離が近いリーダーの存在は、利用定着を大きく後押しします。
- 部門ごとにシステム推進担当を任命
- 推進担当に定期的なフォロー会を実施
- 問題対応の一次窓口として機能させる
- 推進担当向け勉強会や情報交換会を実施
4.6. 定期的な振り返りと改善のサイクルを組み込む
一度きりの対処で終わらせず、利用状況をモニタリングしながら継続的な改善活動を仕組みに組み込むことが大切です。
PDCAを意識した運用で、システムが常に現場にフィットする状態を保ちましょう。
- 月次での利用状況レポートを作成する
- 利用部門との振り返りミーティングを開催する
- トラブル/改善提案の受付チャネルを設置する
- PDCAサイクルを意識した定例運用会議を実施する
社内評価が低いシステム導入も、具体的な改善ステップを踏むことで大きく状況を好転させることが可能です。
現場との対話を重ねながら、日常業務の中で自然に使われる仕組みを目指して運用改善を継続することが、最終的な定着と評価向上の鍵となります。
5. 社内評価が高いシステム導入にするためには?

システム導入を成功させ、現場に受け入れられる状態を最初から作り上げることができれば、評価の低下を未然に防ぐことが可能です。
- 現場の業務フローを理解する
- 操作性とUI/UXに配慮したシステムを選定する
- 利用部門を巻き込みと意見を反映させる
- 導入目的・メリットを明確に伝える
- 十分な初期教育とサポート体制を整備する
- 段階的な展開で負担を軽減する
- 継続的に評価を行う
- 最適なシステム開発会社を選定する
ここからは、社内評価を高めるために、導入前・導入時に意識しておくべきポイントを紹介します。
5.1. 現場の業務フローを理解する
導入前に最も重要なのが、現場の業務内容を正確に把握することです。
紙ベースでの処理が残っているのか、他部門との連携がどうなっているのかなど、実務を深く理解することが、的外れな機能追加や仕様決定を避けるカギとなります。
- 実作業とシステム化のギャップを把握する
- 既存ツールや手作業フローを洗い出す
- ユースケースをもとに画面遷移や操作手順を整理する
これにより、導入後の運用定着率が上がり、手戻りや改修の工数削減にもつながります。
5.2. 操作性とUI/UXに配慮したシステムを選定する
「誰でも直感的に使える」「ミスが起きにくい」「画面が見やすい」といった操作性・視認性への配慮は、現場のストレス軽減に直結します。
専門知識がなくても使える設計かどうかを必ず確認しましょう。
- マウスやタッチで直感的に操作できるUI
- 操作ミスを防ぐアラートや確認メッセージの表示
- モバイルやタブレット対応による利便性の向上
結果として、現場の負荷を減らし、システム離れを防止できます。
5.3. 利用部門を巻き込みと意見を反映させる
利用する部門や現場の意見を導入前から取り入れることで、「自分たちが関わったシステム」という意識が生まれ、協力体制が整いやすくなります。
ヒアリングや検証の場に現場代表を必ず含めましょう。
- プロトタイプや画面モックを使った現場レビューを実施する
- 機能優先度の決定に現場意見を反映させる
- 操作テストに実務担当者を参加させる
導入段階での納得感が高まり、導入後の協力体制もスムーズになります。
5.4. 導入目的・メリットを明確に伝える
「なぜ導入するのか」「導入によって何が良くなるのか」を、全社に対して分かりやすく説明し、納得感を醸成します。
目的と期待効果を具体的な数字や業務例で示すと効果的です。
- 導入目的と期待効果を明文化する
- 成果目標をKPIとして可視化する
- 定例会や社内広報で目的と背景を周知する
社員のモチベーション向上と導入後の活用促進につながります。
5.5. 十分な初期教育とサポート体制を整備する
新しいシステムに対して不安を抱えるのは当然です。
操作マニュアル、FAQ、研修、専用サポート窓口を整備し、安心して使い始められるようにします。
- オンライン・対面の初期研修を複数回実施する
- 操作手順の動画や簡易マニュアルを提供する
- 利用初期フェーズの問い合わせ対応体制を構築する
安心して使える環境づくりが、システム定着の第一歩です。
5.6. 段階的な展開で負担を軽減する
最初から全社一斉導入ではなく、特定部署からスモールスタートさせましょう。
課題を抽出し、改良しながら展開する方式をとることで、現場の混乱を抑えられます。
- パイロット部門を決めて段階的に導入する
- テスト運用中に現場からの改善点を収集する
- 全社展開時に改善版を反映し、初期トラブルを最小化する
現場への負荷が抑えられることで、受け入れやすさが大きく向上します。
5.7. 継続的に評価を行う
導入後も、利用状況や課題を定期的にチェックする仕組みを設けましょう。
システムが本来の目的を果たしているか、現場にとって今も有用かを評価し、改善点があれば早期に対応します。
- 利用率・操作ログを分析する
- 現場アンケートやヒアリングで実態を把握する
- 定例会での課題・改善点の報告と共有する
こうした継続的な見直しが、システムの活用度と満足度を高めていきます。
5.8. 最適なシステム開発会社を選定する
開発会社の選定は、導入成功の重要な要素です。
業務理解力、提案力、UI設計力、サポート対応力などを総合的に評価し、価格だけで選ばないことが肝心です。
- 同業種での導入実績があるか確認
- 提案内容に現場視点や業務改善の観点があるか
- 導入後の運用支援体制があるか
信頼できるパートナー選びが、導入後の運用成功を大きく左右します。
システムを「成果を生む仕組み」として根付かせることで、業務改善や組織の変革推進を実現できます。
社内評価を高めるシステム導入には、多角的な視点が必要です。
自社だけで判断せず、システム開発会社などの第三者からの意見を参考にするようにしましょう。
6. 社内評価が高いシステム導入にするためのシステム開発会社選び

理想的なシステム導入の実現には、信頼できる開発会社の選定が不可欠です。
どれだけ社内で準備を整えても、開発パートナーの質によってプロジェクトの成果は大きく左右されます。
- 現場理解と業務改善提案ができるか
- ユーザ視点のUI/UX設計に強いか
- スモールスタートやPoCに柔軟
- 導入後のサポート・運用支援が手厚いか
- 対話力と提案力に優れているか
ここでは、社内評価の高いシステムを実現するために押さえておきたいシステム開発会社選びのポイントを解説します。
6.1. 現場理解と業務改善提案ができるか
単なるシステム開発の技術力だけではなく、クライアントの業務内容や課題を正しく理解し、改善提案ができるパートナーであるかが重要です。

- ヒアリングを通じて業務内容を丁寧に把握しているか
- 業務改善”にフォーカスした提案ができているか
- 課題に対して具体的な改善策を提示できているか
現場に寄り添った提案ができる企業は、業務にフィットし、運用定着率の高いシステムを構築できます。
6.2. ユーザ視点のUI/UX設計に強いか
見た目の美しさだけでなく、誰でも迷わず操作できるユーザ体験(UX)を提供できる設計力があるかを確認しましょう。

- UIプロトタイプを提供し、ユーザテストを重ねているか
- 操作導線がシンプルで、現場からのフィードバックを反映しているか
- 高齢者やITに不慣れなユーザにも配慮されているか
UI/UXに配慮されたシステムは、現場でのストレスを減らし、定着率向上に貢献します。
6.3. スモールスタートやPoCに柔軟
全社展開を前提とせず、小規模な導入から始めて改善・拡張していく方式に柔軟に対応できる会社を選ぶことで、リスクを最小限に抑えながら確実に成果を出せます。

- PoC(概念実証)やパイロット導入に対応可能か
- 改善を前提にしたアジャイル型の進め方ができるか
- 小規模運用の結果をもとに改善案を提案してくれるか
段階的導入に協力的な会社かどうかは重要な見極めポイントです。
6.4. 導入後のサポート・運用支援が手厚いか
導入して終わりではなく、導入後の運用支援やトラブル対応にどれだけ力を入れているかも、会社選びの基準となります。

- サポート窓口の応答スピードや対応範囲を明示しているか
- 操作ミスや障害時の復旧サポートが整っているか
- 定期的な保守・バージョンアップ対応が含まれているか
定着まで伴走してくれるパートナーかどうかを確認しましょう。
6.5. 対話力と提案力に優れているか
要望をそのまま実装するのではなく、課題の本質を捉えて提案できる「対話力」と「提案力」のある会社は信頼に値します。

- クライアントの業務や文化を理解したうえで提案してくれるか
- 技術用語ばかりでなく、誰にでも伝わる説明をしてくれるか
- 対話を通じて要件を深掘りし、代替案を提示できるか
クライアントの意図をくみ取る力、伝える力がプロジェクト成功の鍵になります。
6.6. 業界・業種に特化した実績があるか
業種によって業務フローや法規制が異なるため、同業他社への導入経験があるかどうかは重要な判断基準になります。

- 自社と同業種での導入実績が豊富か
- 業界特有の課題や要件に精通しているか
- 実績紹介や導入事例などを具体的に提示できるか
特化実績のある企業は、導入時のトラブルを減らし、短期間で成果を出すことができます。
6.7. セキュリティ・法令対応力があるか
近年では、情報漏えいや電子帳簿保存法、個人情報保護法などの対応も求められます。
十分なセキュリティ対策が講じられているかは重要なポイントです。

- ISMSやPマークなどの取得実績があるか
- インボイス制度や電子帳簿保存法への対応経験があるか
- セキュリティ事故発生時の対応体制が明確か
システムの安全性やコンプライアンス対応は、長期運用における信用の土台となります。
6.8. 拡張性・スケーラビリティを設計に組み込めるか
初期段階の要件だけでなく、将来的な業務拡大や変化にも柔軟に対応できる設計力も必要です。

- 業務変更に応じた機能追加がしやすい構成になっているか
- 他システムとのAPI連携・データ連携が可能か
- 機能をモジュール化して必要に応じて入れ替え可能か
拡張性がある設計は、長期にわたって価値を発揮するシステムづくりに欠かせません。
高評価なシステム導入には、システム開発会社の選定が重要です。
業務理解、UI/UX設計、柔軟な進行、導入後支援、提案力に加え、業界実績・法令対応力・拡張性という視点でも見極めましょう。
信頼できる開発パートナーとタッグを組むことで、現場に根付き、長期的に活用されるシステムを実現できます。
7. システム導入の社内評価が低いことにお悩みなら「ブリエ」

「せっかく時間とコストをかけてシステムを導入したのに、現場からの不満が多い」「結局、使われずに形骸化してしまった」
そんなお悩みを抱えている企業の方は、ぜひ一度「ブリエ」にご相談ください。
ブリエでは、単なるシステム導入にとどまらず、現場定着と成果創出までを見据えたトータルサポートを提供しています。
- 現場ヒアリングから丁寧に実施し、業務フローを可視化
- 利用者目線のUI/UX設計で、誰でも使いやすいシステムを構築
- 導入目的やKPIの明確化支援により、社内の納得感を醸成
- 教育・マニュアル作成・運用支援までを一気通貫でサポート
- 継続的な運用改善・アフターフォロー体制が充実
「既に導入済みのシステムがうまく活用されていない」「今後の導入に向けて現場と連携を強化したい」といったケースでも、多くの実績がございます。
社内評価の高いシステム運用を実現したい企業様は、ぜひブリエにご相談ください。
8. まとめ
- 導入前後の準備と社内コミュニケーションが不足している
- 現場の業務フローとシステムの機能が合っていないケースが多い
- 「使いづらい」「何のためか分からない」という現場の声が放置されがち
- UIが複雑で操作が直感的でない
- 導入目的やメリットが社内に共有されていない
- 初期研修・教育が不十分で使いこなせない
- サポート体制が弱く、問い合わせ先が不明瞭
- トップダウン導入で現場の納得感がない
- 運用ルールが曖昧で属人化する
- データ移行や初期設定でつまずき、印象が悪くなる
- 現場業務の流れを正確に把握してから設計する
- ユーザ視点のUI/UX設計を意識する
- 利用部門を巻き込んで導入プロセスを進める
- 教育とフォローを段階的に丁寧に行う
- プロトタイプを活用したレビューの実施
- パイロット運用による段階的展開
- KPIを設定して成果を可視化
- 定期的な評価と改善のサイクルを設ける
- 同業界での実績がある開発会社を選定
- 導入後も運用までサポートできる体制があるか確認
- 現場理解と提案力を持つ担当者の有無がカギ
システム導入の成否は、単なる開発や実装にとどまらず、「現場との対話」と「継続的な運用支援」にかかっています。
現場に寄り添った設計とプロセスこそが、社内評価の高いシステムを実現するカギです。
信頼できるパートナーとともに、評価されるシステム導入を目指しましょう。

株式会社ブリエ代表取締役。Webデザイン、WordPress、Elementor、DTPデザイン、カメラマンなどを経て、FileMakerエンジニアとなる。企業の経営課題であるDX化、業務効率化、ペーパーレス化、情報の一元管理など、ビジネスニーズの変化に合わせてFileMakerで業務システムを開発し、柔軟に拡張して解決いたします。







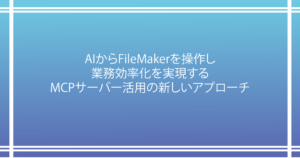
-300x200.jpg)

-1024x290.png)