
FileMakerエンジニア

中小企業にとってDX(デジタルトランスフォーメーション)は、今すぐにでも取り組むべき経営課題です。
人手不足やアナログ業務の限界、意思決定の遅れなどに悩む声は少なくありません。
特に中小企業はリソースが限られる分、こうした課題がより深刻に現れやすい傾向があります。
- 人手不足で業務が回らず、残業や属人化が常態化している
- 紙やExcel中心で転記ミス・確認作業が多く、生産性が上がらない
- チャネルや拠点ごとにシステムがバラバラで、データがつながらない
- リアルタイムに数字が見えず、勘と経験に頼った意思決定になっている
- セキュリティや権限管理が曖昧で、情報漏えいリスクが不安
こうした課題は、現場起点のDX化で着実に解消できます。
- 中小企業がDX化に踏み出すべき理由
- DX化で得られる効果
- 失敗しないための導入ステップ
- ツール選定の要点や活用できる制度/補助金
本記事では、中小企業がDX化に踏み出す理由から、実際に成果が出た事例、失敗しない導入ステップ、効果を最大化するツール選定のポイント、そして進める際の注意点までを体系的に解説します。
自社のDX化を「どこから、どう始めるか」が具体的に見えるはずですので、ぜひ参考になさってください。
目次
1. 中小企業のDX化が必要な理由

中小企業にとってDX化(デジタルトランスフォーメーション)は、もはや選択肢ではなく必須の取り組みとなりつつあります。
ここでは、中小企業がDX化を進めるべき主な理由を整理します。
1.1. 人手不足と労働生産性の低さ
少子高齢化が進む日本では、中小企業を中心に深刻な人手不足が続いています。
採用活動を強化しても人材確保が難しく、既存社員に過度な負担がかかるケースが多く見られます。
結果として、残業の常態化や離職率の上昇につながり、さらなる人材不足の悪循環に陥る可能性があります。
DX化によって業務プロセスを自動化・効率化すれば、少人数でも高い生産性を維持できます。
人手不足を単純に「人を増やす」ことで解決するのではなく、「既存の人材でより効率的に業務を回す」方向へ転換することが求められているのです。
1.2. アナログ業務の限界
中小企業では、依然として紙書類やExcelによる業務管理が多く残っています。
しかし、これらは転記作業や二重入力を生み、ヒューマンエラーの温床となります。
特に在庫管理や受発注業務では「データが最新化されない」「担当者が不在だと状況がわからない」といった課題が頻発します。
こうしたアナログ業務には限界があり、デジタル化による効率化が不可欠です。
DX化によってクラウドシステムを活用すれば、リアルタイムで情報を共有でき、属人化を防ぐことが可能になります。
1.3. 顧客ニーズの多様化
インターネットやSNSの普及により、顧客の購買行動やニーズは急速に多様化しています。
価格や品質だけでなく、利便性・スピード・体験価値といった要素が意思決定に影響を与えるようになりました。
中小企業がこうした変化に対応するには、データに基づいて顧客行動を分析し、柔軟にサービスや商品を改善する必要があります。
DX化によって顧客管理やマーケティングを強化すれば、個別ニーズに応じたサービス提供が可能となり、大手企業との差別化にもつながります。
1.4. 経営判断の遅れ
従来の中小企業では「勘と経験」に基づいた経営判断を行うことも少なくありませんでした。
しかし、市場環境が変化するスピードが速まる中、このような意思決定では対応が遅れ、機会損失や競争力低下につながります。
DX化により販売データ・在庫データ・顧客データを統合すれば、経営者はリアルタイムで経営状況を把握できます。
データドリブンな意思決定が可能となり、変化に迅速かつ正確に対応できるようになります。
1.5. 持続的成長への対応
中小企業が長期的に成長していくためには、単に現状の効率化にとどまらず、新しいビジネスモデルや収益源を模索することが求められます。
デジタル技術を活用すれば、新サービスの開発や新市場の開拓が容易になり、持続的な成長を実現できます。
また、国や自治体も中小企業のDX化を後押ししており、補助金や支援制度が整いつつあります。
こうした外部環境の変化もまた、中小企業がDX化に取り組む必要性を高めている大きな要因です。
2. 中小企業がDX化で得られる効果

DX化は単なるITツールの導入ではなく、業務フローや企業の体質そのものを変える取り組みです。
そのため効果は一部の業務効率化にとどまらず、経営全体に波及します。
ここでは中小企業がDX化によって得られる具体的な効果を解説します。
2.1. 業務効率化と生産性向上
最も大きな効果は、日常業務の効率化です。これまで紙やExcelで行っていた作業をシステムに置き換えることで、入力・転記の手間やヒューマンエラーを大幅に削減できます。
たとえば在庫管理をクラウド化すれば、入出庫の記録が自動で反映され、担当者は確認作業にかける時間を減らせます。
その分、営業活動や新規顧客開拓といった付加価値の高い業務に時間を割けるようになり、企業全体の生産性向上につながります。
- 棚卸し作業時間を従来の半分以下に削減
- 入力/確認作業を自動化し、ヒューマンエラーを大幅に減少
- 空いた時間を営業・顧客対応に振り分け、生産性を向上
2.2. コスト削減と利益率の改善
業務の効率化は、コスト削減にも直結します。
人件費や紙・印刷費などの削減はもちろん、二重入力や確認作業の削減によって残業時間も減り、トータルコストが抑えられます。
さらに在庫の最適化や受発注の自動化により「余剰在庫」や「欠品による機会損失」を減らすことも可能です。
これは売上を維持しながら原価を下げることにつながり、利益率改善に直結する効果です。
- 年間数百万円規模の在庫保管コストを削減
- 紙/印刷費などの間接コストを削減
- 残業時間削減により人件費を圧縮し、利益率を改善
2.3. 人材不足の解消と属人化からの脱却
中小企業にとって人材不足は大きな課題ですが、DX化はその解決策となり得ます。
自動化によって少人数でも業務を回せる体制を整えれば、新たに人を増やさなくても既存人員で対応可能になります。
また、情報をクラウドに集約し、業務フローをシステムに組み込むことで「特定の担当者しかできない仕事」を減らせるでしょう。
属人化の解消は引き継ぎや人員交代を容易にし、組織としての安定性を高めます。
- 自動化で1人あたりの業務処理量が増加し、採用コストを削減
- 担当者交代時の引き継ぎ時間を大幅短縮
- 退職や異動があっても業務が滞らない体制を構築
2.4. 顧客体験・サービス品質の向上
DX化は社内業務だけでなく、顧客体験の向上にも直結します。
たとえば、予約管理システムを導入すれば顧客は24時間オンラインで予約でき、利便性が高まります。
ECサイトと実店舗の在庫を一元化すれば「注文したのに欠品だった」といった在庫トラブルを回避し、満足度の低下を防ぐことができます。
顧客からの問い合わせ対応をチャットボットやCRMで効率化することも可能です。
迅速で一貫性のある対応は顧客の信頼を高め、リピート率の向上にもつながります。
- 24時間予約受付で顧客満足度を向上
- 欠品や在庫トラブルを削減し、クレーム件数を減少
- リピート率が10〜20%改善
2.5. データ活用による迅速かつ正確な経営判断
販売データや在庫データ、顧客データをシステムで統合することで、経営者はリアルタイムに数字を把握できます。
これにより「在庫が減っているので発注を早める」「売れ筋商品に集中投資する」といった迅速で正確な判断が可能になります。
従来のように月次や四半期単位で数字を集計してから判断していては、市場変化に追いつけません。
DX化はデータドリブンな経営を実現し、意思決定のスピードと精度を飛躍的に高めます。
- 経営会議用の資料作成を数日から数時間に短縮
- 売れ筋商品の把握により、在庫回転率を改善
- 予測精度が向上し、発注ミスや機会損失を減少
2.6. 持続的成長と競争力強化
効率化・コスト削減・顧客満足度向上といった効果は、最終的に企業の競争力強化につながります。
大企業だけでなく中小企業もデジタル技術を活用することで、スピード感のあるサービス提供や市場変化への柔軟な対応が可能になります。
特に同業他社がDX化を進める中、自社だけが取り残されれば競争力を失うリスクがあります。
逆に早期にDX化に取り組めば業界内で優位性を確保でき、持続的な成長につながります。
- 市場シェアの拡大による売上増加
- 新規顧客獲得のスピードアップ
- 業界内での競争優位性を確保
2.7. 新しいビジネスモデルの創出
DX化は単なる効率化にとどまらず、新たなビジネスモデルを生み出す基盤にもなります。
クラウドサービスを活用してサブスクリプション型のサービスを展開したり、IoTを活用して新しい製品価値を提供したりすることも可能です。
中小企業にとって新規事業の立ち上げはリスクが大きいですが、デジタル技術を使えば小さく始めてスピーディーに改善できるため、従来よりも挑戦しやすくなります。
これは将来的な成長の機会を広げる大きな効果といえます。
- サブスクリプション型サービスで安定収益を確保
- IoT連携による新製品・新サービスの開発
- デジタル活用で新市場への進出が容易に
3. 中小企業のDX化における課題

中小企業がDX化を進める必要性や効果は明らかですが、実際には多くの企業が導入に苦戦しています。
ここでは、中小企業がDX化を推進する際に直面しやすい代表的な課題を整理します。
3.1. 導入コストや予算の制約
中小企業がDX化に踏み出せない最大の理由の一つが「コスト」です。
システム導入には初期費用がかかり、さらに運用・保守のためのランニングコストも発生します。
大企業と比べ資金的余裕が少ない中小企業にとっては、短期的な費用負担が大きなハードルとなります。
また、「どの程度の費用対効果があるのか」が明確に見えないまま投資判断を迫られるケースも多く、意思決定が遅れる要因になります。
- 設備投資に回せる資金が限られている
- 初期費用を回収できるかどうかの不安が大きい
- 補助金や助成金の情報収集/申請に時間と手間がかかる
3.2. DX人材の不足
DX化を推進するには、ITスキルやデータ活用の知識を持った人材が欠かせません。
しかし現実には、多くの中小企業で専門人材が不足しています。
社内に担当者を置けず、既存社員が通常業務の合間にDX推進を担うことも少なくありません。
結果として、プロジェクトが思うように進まなかったり、外部ベンダー任せになり自社にノウハウが残らなかったりするリスクが生じます。
- IT専門人材を採用する余裕がない
- 社員が兼務でDXを担当し、本業に支障が出る
- 外部ベンダー依存度が高まり、自社にノウハウが蓄積しない
3.3. 社内の抵抗感・文化的課題
DX化は単なるシステム導入ではなく、業務プロセスや働き方そのものを変える取り組みです。
そのため「従来のやり方に慣れた社員」からの抵抗が発生することは珍しくありません。
「新しいシステムは難しそう」「これまでのやり方で問題なかった」といった心理的ハードルは、特に現場で根強く存在します。
経営層がDXの意義を正しく伝え、社内全体で取り組む姿勢を醸成できなければ、導入効果は限定的になってしまいます。
- デジタルに不慣れな社員が多い
- 少人数のため反対意見が浸透しやすい
- 経営者がITに詳しくなく、推進力を欠く
3.4. 部分最適によるシステム乱立
中小企業では「とりあえず便利そうだから」と部門単位でツールを導入するケースが少なくありません。
結果として、在庫管理はAシステム、販売管理はBシステム、顧客管理はExcel、といった具合にバラバラの環境ができあがります。
このような「部分最適」の状態では、データが連携せず二重管理が発生したり、全体像を把握できなくなったりします。
本来のDX化は全社的な業務最適化を目指すものですが、システム乱立はその逆を招いてしまう典型的な課題です。
- 部門横断でシステムを統一する仕組みがな
- IT投資の意思決定が短期的で場当たり的になりやすい
- 導入後の運用/管理を担う人材がいない
3.5. セキュリティやガバナンスの不安
DX化によって業務がクラウド化・オンライン化すると、サイバーセキュリティや情報漏えいリスクが高まります。
特に中小企業はセキュリティ専門人材を抱える余裕が少なく、対策が後回しになることが多いのが現状です。
また、情報管理ルールや権限設定が曖昧なままシステムを導入すると、内部不正やデータの誤操作といったリスクも増えます。
DX化を進めるうえでは、利便性とセキュリティのバランスをとりながらガバナンスを確立することが欠かせません。
- 専門人材や専任部署を置けないためセキュリティ対応が遅れる
- コスト優先で最低限のセキュリティに留まりやすい
- ガバナンス体制やルール作りが後回しにされがち
4. 中小企業のDX化事例

DX化の必要性や効果を理解しても、「実際に自社にどう活かせるのか」がイメージしづらいという声は少なくありません。
ここでは、中小企業が取り組みやすい代表的なDX化の事例を紹介します。
どれも現場の課題を解消し、業務効率化や顧客満足度向上につながったケースです。
4.1. 在庫管理・生産管理業務のDX化
中小企業の現場で最も多く聞かれる悩みの一つが、在庫や生産の管理です。
紙やExcelに頼る管理方法には、見過ごせない問題が潜んでいます。
課題:紙やExcelで在庫や生産を管理しているため、入出庫の記録が遅れたり、在庫数と実際の数量が合わなくなるケースが頻発。
結果として、欠品や過剰在庫が発生し、販売機会の損失やコスト増加につながっていました。
| 解決策 | クラウド型の在庫管理システムを導入し、バーコードやQRコードで入出庫を自動記録。 生産管理もシステムに組み込むことで、リアルタイムに在庫数を把握できるようにしました。 |
| 効果 |
|
4.2. 販売管理業務のDX化
近年、ECと実店舗を同時に運営する中小企業が増えていますが、その裏で「在庫や売上管理の分断」による混乱が少なくありません。
課題:ECサイトと実店舗を並行して運営している企業では、販売チャネルごとに在庫を分けて管理しているケースが多く、更新の遅れから「ネットで注文された商品が実は在庫切れだった」というトラブルが発生していました。
| 解決策 | 販売管理システムを導入し、ECと店舗の在庫を一元管理。 売上データも自動的に集計され、販売状況をリアルタイムで把握できる体制を構築しました。 |
| 効果 |
|
4.3. 現場進捗管理業務のDX化
建設業や製造業といった「現場を持つ企業」では、日々の進捗共有が経営に直結します。
しかし従来のやり方では、情報伝達に遅れが生じることが少なくありません。
課題:建設業や製造業では、現場ごとの作業進捗が口頭やFAXで共有されることが多く、情報伝達の遅れや認識のずれが発生していました。
経営層が現場の状況を把握できず、判断が遅れるケースもありました。
| 解決策 | モバイルアプリを活用し、現場から進捗を写真やコメント付きで登録できる仕組みを導入。 データはクラウドに自動反映され、本社と現場が同時に状況を共有できるようにしました。 |
| 効果 |
|
4.4. 顧客管理業務のDX化
顧客管理は取引先との関係を支える重要な業務です。
しかし、中小企業では担当者に依存した管理体制が多く、属人化が大きな障害となっています。
課題:顧客情報を紙の名簿やExcelで管理していたため、「過去の取引履歴が担当者しかわからない」「問い合わせ対応に時間がかかる」といった属人化の問題が発生していました。
| 解決策 |
CRM(顧客管理システム)を導入し、顧客情報・取引履歴・問い合わせ内容を一元管理。 営業やカスタマーサポートが同じ情報をリアルタイムで確認できる体制を構築しました。 |
| 効果 |
|
4.5. 請求・会計業務のDX化
経理部門は中小企業の中でも特に業務負担が大きい分野です。
請求や会計業務を手作業で処理していると、作業効率と精度の両面で大きな課題が浮き彫りになります。
課題:請求書を手作業で作成・郵送していたため、発行作業に時間がかかり、月末月初に経理部門の負担が集中していました。
また入力ミスや送付漏れが発生しやすく、取引先とのトラブルの原因にもなっていました。
| 解決策 |
請求書発行システムを導入し、取引データから自動で請求書を作成・送付できる仕組みを構築。 クラウド会計ソフトとも連携し、入金確認や仕訳作業も自動化しました。 |
| 効果 |
|
5. 中小企業のDX化を成功させるための導入ステップ
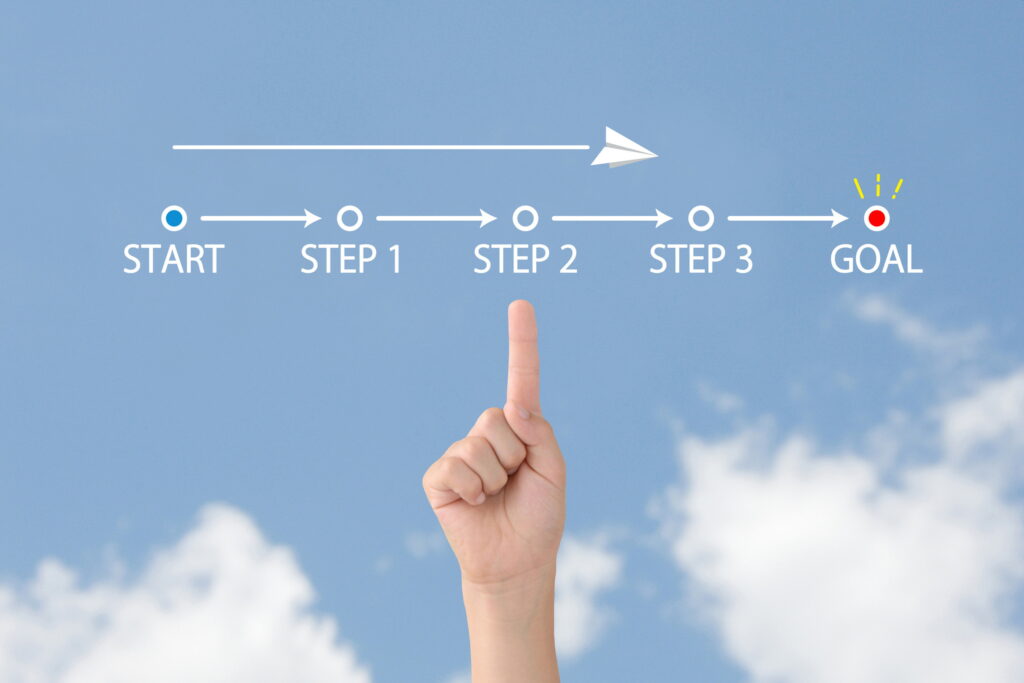
DX化は「システムを導入すれば自動的に進む」というものではありません。
明確な目的設定と段階的な進め方が重要です。
ここでは、中小企業がDX化を進める際に押さえておきたい導入ステップを解説します。
5.1. 現状業務の課題洗い出し
最初のステップは、現状の業務フローを可視化し、課題を明確にすることです。
- どの業務に時間がかかっているのか
- どこでミスが発生しているのか
- どの情報が属人化しているのか
- 取引先や顧客からのクレームが多い業務はどこか
この工程を省略すると、導入後に「本当に解決したかった問題が改善されない」という事態に陥りがちです。
現場担当者を巻き込み、実態を明らかにすることが成功の第一歩です。
5.2. DX化の目的とゴールを明確化
次に、DX化によって何を実現したいのかを具体化します。
数値目標を盛り込むと効果測定がしやすくなります。
- 業務時間を月○時間削減する
- 在庫差異を○%以内に抑える
- 顧客満足度調査でスコアを○点改善する
- 売上高を前年比○%向上させる
曖昧なまま進めると「システムを入れること自体が目的化」してしまい、効果が実感できないまま終わるリスクがあります。
経営層と現場でゴールを共有することが重要です。
5.3. 小さく始めてスモールスタート
いきなり全社的に導入するとリスクが大きいため、まずは一部業務から着手するのが現実的です。
- 請求書の電子化から導入する
- 次の段階で在庫管理システムを連携する
- 最終的に販売管理や会計とも統合する
小さな成功体験を積み重ねることで、社員の理解と協力が得やすくなります。
5.4. 社内体制の整備とDX人材の育成
DX化を成功させるには、システムだけでなく「人と組織」の準備が不可欠です。
- プロジェクトリーダーを任命する
- 部門横断で推進チームをつくる
- DX担当者に研修を行う
- 外部アドバイザーやITコンサルを一時的に活用する
外部ベンダーに依存するのではなく、社内にノウハウを残す仕組みを意識することが大切です。
人材を育成し、体制を整えることで導入後の定着度も高まります。
5.5. 導入システムの選定ポイント
システム選定では、導入後の業務定着や将来の拡張性まで見据えることが大切です。
- 自社の業務フローに合っているか(無理にシステムに合わせない)
- 拡張性があるか(将来的な機能追加に対応できるか)
- 他システムと連携できるか(販売管理、会計などとつながるか)
- 使いやすいか(現場社員が直感的に操作できるか)
- サポート体制(トラブル対応・運用支援の有無)
- 導入企業の事例や評判(同業種での実績があるか)
複数ベンダーから提案を受け、PoC(概念実証)を行うことで失敗リスクを減らせます。
5.6. 効果測定と継続的改善
導入後は「入れて終わり」にせず、定期的に効果を測定し、改善を重ねていくことが重要です。
- 業務時間はどのくらい削減されたか
- エラー率はどの程度減ったか
- 顧客対応スピードや満足度は改善されたか
- 売上や利益率に変化があったか
もし効果が限定的であれば、システムの使い方や業務フロー自体を見直す必要があります。
PDCAを回し続けることで、DX化は一度きりの投資ではなく、持続的な改善サイクルとして機能します。
6. 中小企業のDX化に活用できるツールとシステム

DX化を進める上で欠かせないのが「デジタルツールやシステム」の活用です。
中小企業にとっては高額な専用システムを構築するよりも、クラウド型やサブスクリプション型のサービスを導入する方が現実的です。
ここでは代表的なツールとその活用方法を紹介します。
6.1. クラウド型基幹システムの活用
クラウド型基幹システムは、販売・在庫・会計・人事など複数の業務を一元管理できるシステムです。
従来は大企業向けのイメージが強かったERPも、クラウド型で提供されることで中小企業でも導入しやすくなっています。
- インターネット環境があればどこからでも利用できる
- 複数拠点やリモートワークに対応可能
- 部門ごとに分断されていたデータを統合し、経営状況をリアルタイムに把握できる
6.2. RPAツールの活用(業務自動化)
RPA(業務自動化)は、人がパソコンで行っている定型作業をソフトウェアロボットに代行させる仕組みです。
たとえば請求書の発行や受注データの入力など、繰り返し作業を自動化できます。
- 単純作業を自動化し、人手不足の解消につながる
- 人的ミスを削減し、正確性を確保できる
- 社員は付加価値の高い業務に時間を割けるようになる
6.3. BIツールの活用(データ分析)
BI(データ分析)ツールは、販売データや在庫データなどを集計・可視化するツールです。
Excelなどでは時間がかかる分析を、瞬時にグラフやダッシュボードで確認できます。
- 売上や在庫の傾向をリアルタイムで把握できる
- データに基づいた戦略立案が可能になる
- 勘や経験に頼らない意思決定ができる
6.4. ローコード・ノーコード開発ツールの活用
ローコード・ノーコードツールは、専門的なプログラミング知識がなくてもアプリや業務システムを構築できる開発環境です。
現場の社員が自ら業務に合わせたアプリを作成できるため、中小企業の「DX人材不足」を補う有効な手段となります。
- 現場の声を反映した業務アプリを迅速に構築できる
- 外部ベンダーに依頼せず、コスト削減につながる
- 社内で改善サイクルを回しやすくなる
6.5. モバイルアプリ・タブレットの活用
現場での情報共有や作業効率化には、モバイルアプリやタブレットの活用が欠かせません。
建設現場や製造現場、小売店舗などで、作業報告や在庫確認をその場で行えるようになります。
- 現場でリアルタイムにデータを入力・共有できる
- 情報のタイムラグをなくし、判断スピードを向上させる
- 顧客対応や接客の質を高め、満足度向上につながる
ここで紹介したツールやシステムは、いずれも中小企業がDX化を進める上で有効な手段です。
ただし、自社の業務内容や組織規模、将来の成長戦略によって「最適な組み合わせ」は異なります。
- 業務フローに合ったシステムを選ぶこと
- 将来の拡張性や連携性を考慮すること
- 現場が無理なく使える仕組みを導入すること
これらを押さえることで、DX化の効果を最大化できます。
自社にとって最適なシステムやツールを選定する際には、経験豊富なシステム開発会社へ相談することが有効です。
専門知見を取り入れることで導入の失敗を防ぎ、より実効性のあるDX化を実現できます。
なお、株式会社ブリエでは、無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
7. 中小企業がDX化を進める際の注意点

DX化は大きなメリットをもたらしますが、導入プロセスを誤ると「期待した効果が出ない」「かえって混乱する」といった失敗につながります。
ここでは、中小企業がDX化を進める際に押さえておくべき注意点を解説します。
7.1. システム導入を目的化しない
DX化は課題解決と業務改善のために行うものですが、システムを導入すること自体が目的化してしまうケースが少なくありません。
これでは投資対効果を得られず、現場のモチベーションも下がってしまいます。
- 「他社が導入しているから」と明確な目的を持たずにシステムを導入し、効果が見えなかった
- 高機能なシステムを導入したが、現場に必要な機能が使われず宝の持ち腐れになった
- 効果測定を行わず、導入の成否を検証しないまま改善につながらなかった
- 導入前に「解決すべき課題」と「数値目標」を明確化する
- 導入後の効果を測定する仕組みを計画段階から組み込む
- 現場の声を反映し、実際の業務に直結する目標を設定する
7.2. ベンダーロックインを回避する
外部ベンダーに依存しすぎると、自社の裁量でシステムを運用できなくなり、コストや柔軟性の面で大きなリスクとなります。
契約条件を精査せずに導入するのは危険です。
- 契約更新時に他社へ移行できず、不利な条件を受け入れざるを得なかった
- ソースコードや設定情報がベンダーにしか分からず、改修のたびに高額費用を請求された
- 独自仕様のシステムを選んだ結果、他ツールと連携できず業務が分断された
- 契約時に「データの持ち出し可否」や「移行条件」を確認する
- API連携や標準規格に対応したシステムを選ぶ
- 複数ベンダーの提案を比較し、依存度を下げる
7.3. 社内浸透を優先する仕組みをつくる
システムは導入して終わりではなく、実際に社員が活用できて初めて成果が出ます。
教育や説明を省略すると、現場の反発や非協力につながります。
- 研修を行わずに導入したため、社員が操作方法を理解できず業務効率が下がった
- 現場に導入の意義を説明せず「経営層の押し付け」と受け取られ、利用が定着しなかった
- サポート体制を整えなかったため、トラブル時に社員がシステムを避けるようになった
- 導入時に研修やマニュアルを整備する
- 社員に導入の目的やメリットを丁寧に共有する
- 小さな業務から始めて、現場に成功体験を積ませる
7.4. 段階的に導入し改善を重ねる
中小企業はリソースが限られているため、一度に大規模なシステム導入を進めると業務に支障をきたします。
段階的に導入し、改善を繰り返すことが重要です。
- 会計/販売/在庫/人事を一斉に切り替え、社内で混乱が発生した
- データ移行に時間がかかり、旧システムと新システムの二重運用が長期化した
- 移行スケジュールを曖昧にした結果、プロジェクト全体が遅延した
- まずは小規模な業務から導入し、効果を確認してから範囲を広げる
- 明確な移行スケジュールを立て、進捗を管理する
- PoC(試験導入)を活用し、トラブルを事前に洗い出す
7.5. セキュリティやガバナンスに配慮する
クラウドサービスやリモートワークが普及する中、セキュリティ対策やガバナンス整備を怠ると深刻なトラブルに直結します。
人材・予算が限られるという理由から後回しにしがちですが、優先度は高いです。
- アクセス権限を設定せず、全社員が機密データを閲覧できる状態になった
- バックアップを取らず、システム障害で重要データを失った
- 情報管理ルールを設けなかったため、内部不正や誤操作でデータが漏えいした
- ユーザ権限を適切に設定し、必要最小限のアクセスに制限する
- 定期的にバックアップを取り、復旧手順を整備する
- 情報管理ルールを策定し、全社員に周知する
- 専門人材が不足する場合は外部のセキュリティサービスを利用する
8. 中小企業のDX化を支援する制度

中小企業がDX化に取り組む際、最大のハードルとなるのが「コスト」と「ノウハウ不足」です。
こうした課題を解消するために、国や自治体はさまざまな制度や補助金を用意しています。
これらを活用することで、導入コストを抑えつつ安心してDX化を進めることが可能です。
8.1. 制度の概要
政府は「デジタル社会の実現」を重点政策のひとつに掲げており、中小企業のDX化を強力に後押ししています。
経済産業省の「DX推進指標」や「DX認定制度」など、企業が自社の取り組みを自己診断したり、外部からの信頼性を高めたりできる仕組みも整備されています。
また、DX推進企業として認定されることで、金融機関からの評価向上や人材採用に有利になるなど、補助金以外の側面でもプラスの効果が期待できます。
このように、制度は資金面の支援にとどまらず、「企業価値向上」や「取引上の信頼性向上」にもつながる点が大きな特徴です。
8.2. 補助金の例
中小企業が利用できる代表的な補助金には、次のようなものがあります。
- IT導入補助金
- ものづくり補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 事業再構築補助金
これらは「DXの初期コストを軽減するための支援」として非常に有効です。
ただし、募集要項や条件は年度ごとに変更されるため、定期的に最新の情報を確認する必要があります。
- 申請には事業計画や数値目標の記載が求められることが多い
- 手続きが煩雑なため、商工会議所や専門家の支援を受けるとスムーズ
- 採択されても補助金は後払いのケースが多く、キャッシュフロー管理に注意が必要
9. 中小企業のDX化ならブリエ

DX化は「どのシステムを選ぶか」だけでなく、「どう導入し、どう定着させるか」が成功を左右します。
特に中小企業の場合、限られた人材・予算の中で進める必要があるため、信頼できるパートナーとともに取り組むことが欠かせません。
株式会社ブリエは、中小企業の課題に寄り添ったシステム開発・DX支援を得意としています。
- ヒアリングを重視し、現場の業務課題を丁寧に整理
- 販売管理/在庫管理/顧客管理/会計など幅広い領域で実績あり
- ローコード/ノーコード開発やクラウド基盤を活用し、コストを抑えた導入が可能
- 導入後も伴走支援を行い、社内への定着をサポート
「システムを導入したのに活用されない」「業務がかえって複雑になった」という失敗を防ぐためには、業務理解と技術力の両方を持つパートナーが不可欠です。
ブリエは、単なるシステム提供にとどまらず、経営と現場をつなぐDX化を推進します。
自社に最適なDX化を進めたいと考えている場合は、ぜひ一度ご相談ください。
10. まとめ
- 人手不足や労働生産性の低さを改善できる
- アナログ業務の限界を解消し、属人化を防ぐ
- 顧客ニーズの多様化や市場変化に柔軟に対応できる
- 勘と経験に頼らない迅速な経営判断が可能になる
- 持続的成長と競争力維持につながる
- 業務効率化と生産性向上
- コスト削減と利益率改善
- 人材不足の解消と安定した業務体制の構築
- 顧客体験やサービス品質の向上
- 新しいビジネスモデル創出による成長機会拡大
- 導入コストや運用コストの負担が大きい
- DX人材が不足し、外部依存が高まるリスク
- 現場社員の抵抗感や文化的ハードル
- 部門ごとの部分最適によるシステム乱立
- セキュリティやガバナンス体制の未整備
- 現状業務の課題を正確に洗い出す
- 目的と数値目標を明確化し、全社で共有する
- スモールスタートで成功体験を積む
- 社内体制を整備し、人材育成を進める
- システム選定は業務適合性/拡張性/連携性を重視する
- 効果測定と改善を繰り返し、継続的に定着させる
DX化は一度きりの施策ではなく、改善を重ねながら定着させることで成果が現れます。
自社に最適な進め方を選び、信頼できるパートナーと共に取り組むことが、持続的成長への近道です。

株式会社ブリエ代表取締役。Webデザイン、WordPress、Elementor、DTPデザイン、カメラマンなどを経て、FileMakerエンジニアとなる。企業の経営課題であるDX化、業務効率化、ペーパーレス化、情報の一元管理など、ビジネスニーズの変化に合わせてFileMakerで業務システムを開発し、柔軟に拡張して解決いたします。







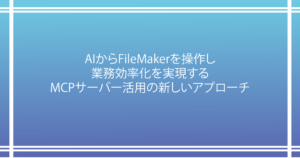
-300x200.jpg)

-1024x290.png)