
FileMakerエンジニア

「法改正への対応」「業務の効率化」「コスト削減」
請求書のペーパーレス化は、もはや選択肢ではなく必須の対応となりつつあります。
しかし、「何を基準にシステムを選べばいいのか?」「現場にフィットする運用ができるのか?」といった不安を抱える企業も少なくありません。
- 改正電子帳簿保存法への対応が不可欠になったため
- 業務のデジタル化・効率化が求められているため
- インボイス制度により記載ルールが厳格化されたため
- 紙による業務の手間・コストが増大しているため
- リモートワークやBCP対策としても有効なた
本記事では、ペーパーレス化を成功に導くためのシステム選定のポイントから、開発会社選びの注意点、信頼できるパートナー企業の紹介まで、実践的な視点で詳しく解説します。
- 電子帳簿保存法に対応するための基本知識
- ペーパーレス化で得られる業務改善のメリット
- システム導入時に直面しやすい課題と対処法
- システム開発会社選定時に見るべき5つの視点
- 現場に寄り添った開発会社「ブリエ」の強み
「形だけの電子化」に終わらせないために、これからの請求業務に必要な視点を、ぜひ本記事でご確認ください。
目次
1. 請求書のペーパーレス化が求められている理由

請求書のペーパーレス化は、単なる業務改善の一環ではなく、法制度や社会的変化に対応するための必須施策となっています。
- 改正電子帳簿保存法による法的対応の必要性
- インボイス制度の導入による請求業務の複雑化
- 業務効率とコスト削減への意識の高まり
- 働き方の多様化とテレワーク対応の必要性
まずは、ペーパーレス化の背景にある法改正や制度導入、業務上の課題やニーズの変化について解説します。
1.1. 改正電子帳簿保存法による法的対応の必要性
2022年1月に改正された電子帳簿保存法では、企業が扱う帳簿や書類を電子的に保存するためのルールを大きく見直されました。
特に注目すべきは、メールやクラウドサービスを通じて受け取った請求書などの「電子取引」について、電子のまま保存することが義務化された点です。
従来のように紙へ出力して保存することは認められなくなり、企業は電子保存の環境を整備しなければ、法令違反となる可能性があります。
請求書を電子的に管理・保存する仕組みづくりは、コンプライアンス上の喫緊の課題です。
企業規模に関係なく、法改正に対応した業務フローの見直しと、適切なシステム導入が求められています。
1.2. インボイス制度の導入による請求業務の複雑化
2023年10月からスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の適用において「適格請求書」の保存を要件としています。
この制度により、請求書の記載事項や保存方法にこれまで以上の正確性と一貫性が求められるようになりました。
手書きやExcelベースの請求書管理では、記載ミスやフォーマットの不統一といったリスクが避けられず、インボイス制度への確実な対応は困難です。
そのため、多くの企業が請求書の電子化・自動化によって制度対応と業務効率化を同時に実現しようとしています。
1.3. 業務効率とコスト削減への意識の高まり
請求書の作成・発行・送付・保管といった一連の業務は、多くの時間と手間、そして紙・封筒・郵送代といったコストを伴います。
これらを電子化することで、作業時間の短縮、ミスの削減、郵送費の削減といった効果が得られ、企業全体の業務効率と生産性の向上につながります。
特に中小企業にとっては、少ないリソースで最大限の成果を出すために、こうした無駄の見直しが重要です。
ペーパーレス化は、単なる書類の電子保存にとどまらず、経営改善の一手にもなり得るのです。
1.4. 働き方の多様化とテレワーク対応の必要性
新型コロナウイルスの影響を契機に、多くの企業でテレワークやハイブリッドワークが普及しました。
それに伴い、オフィスで紙の請求書を確認・処理する前提の業務は、大きな見直しを迫られています。
ペーパーレス化によって、請求書をクラウド上で管理・共有できるようにすれば、場所や時間に縛られず業務を進めることが可能になります。
また、物理的なファイル管理から解放されることで、BCP(事業継続計画)対応や災害対策としても有効です。
これらの背景から、請求書のペーパーレス化は今や「やっておくと便利」ではなく、「やらなければならない」業務改革のひとつとなっているのです。
2. 請求書のペーパーレス化でおさえておきたい改正電子帳簿保存法

改正電子帳簿保存法は、請求書などの取引関連書類を電子データで保存するためのルールを定めた重要な法制度です。
2022年の改正では、電子取引に関する保存義務の強化やスキャナ保存制度の緩和など、実務に直結する大きな変更が加えられました。
- 電子取引の電子保存が義務化された
- スキャナ保存の制度が使いやすくなった
- 保存に必要な要件が明確になった
- 宥恕措置が終了し、対応が必須になった
これらの改正ポイントを正しく理解し、自社の運用に反映させることが、請求書のペーパーレス化を円滑に進めるうえで不可欠です。
詳しく見ていきましょう。
2.1. 電子取引の電子保存が義務化された
電子帳簿保存法の中でも特に実務に大きな影響を与えているのが、電子取引の電子保存義務です。
請求書をデジタルでやり取りする企業にとって、この変更は避けて通れない対応事項となりました。
2022年の法改正により、電子メールやクラウドサービスを通じてやり取りされる請求書などの「電子取引」については、電子データのままでの保存が義務付けられました。
従来のように紙に出力して保存することは認められず、電子データとして適切な方法で保存しなければ、法令違反とみなされる可能性があります。
企業は、法的要件を満たした保存体制の整備が求められており、単にデータをフォルダに保存するだけでは不十分です。
電子帳簿保存法に則った形式で保存し、かつ、必要な際に速やかに閲覧できる状態を保たなければなりません。
2.2. スキャナ保存の制度が使いやすくなった
紙の請求書をスキャンして電子保存する際の制度も、大きく変わりました。
以前は手間がかかり実務に馴染みにくいとされていたスキャナ保存が、法改正を経て現場に取り入れやすくなっています。
従来、紙の書類をスキャナで読み取り保存するには非常に厳格なルールが課されていました。
しかし、今回の法改正により、スキャナ保存に関する制度が大きく緩和され、実務への対応が現実的なものとなりました。
たとえば、保存期限内のタイムスタンプ付与や、定められたフローでの承認・確認、解像度や色階調の条件などが一部簡素化され、より多くの企業がスキャナ保存を選択しやすくなっています。
紙書類をデジタル化する際の負担が軽減され、ペーパーレス化が一層促進されています。
2.3. 保存に必要な要件が明確になった
電子保存に関する基本ルールとして、企業が押さえておくべき2つの要件があります。
それが「真実性の確保」と「可視性の確保」です。法改正によって、これらの内容がより具体的かつ実務で運用しやすい形に整理されました。
電子帳簿保存法では、電子保存が認められるための要件として「真実性の確保」と「可視性の確保」が定められています。
真実性とは、保存したデータが改ざんされていないことを証明することを意味します。具体的には、タイムスタンプの付与や、ログの保存、事務処理規程の整備などが求められます。
可視性とは、保存された書類が必要なときにすぐに閲覧・検索できる状態であることです。
検索機能の要件として、取引年月日・金額・取引先などの条件での検索が可能である必要があります。
これらの要件は改正によって緩和されており、企業が対応しやすくなっています。
2.4. 宥恕措置が終了し、対応が必須になった
改正電子帳簿保存法の施工当初は、実務対応に時間を要することを踏まえた「宥恕措置(ゆうじょそち)」が設けられていましたが、2023年12月末で終了しています。
現在では、すべての企業に法令通りの対応が求められる段階へと移行しました。
保存要件を満たしていない場合、税務調査で指摘を受け、青色申告の承認取消や経費否認といったリスクが生じる可能性があります。
そのため、今後は請求書の電子保存について、確実に要件を満たす体制の構築が必要です。
3. 請求書ペーパーレス化のメリット

請求書を紙から電子へ移行することには、多くの実務的なメリットがあります。
業務効率の向上だけでなく、コスト削減やセキュリティ強化といった観点からも注目されている分野です。
- 保管スペース・管理コストの削減
- 検索性・業務効率の大幅向上
- セキュリティ対策と内部統制強化
- テレワークやBCP(事業継続)への対応強化
ここからは、ペーパーレス化がもたらす主な利点を詳しく解説します。
3.1. 保管スペース・管理コストの削減
紙での請求書管理には、キャビネットや倉庫、専用の保管設備など、多くの物理的スペースと管理コストがかかります。
ペーパーレス化を導入することで、これらの無駄を大幅に削減できます。
- 書類保管用のキャビネットや倉庫が不要になる
- 長期保管にかかる人件費・設備費の削減できる
- オフィススペースの有効活用が可能になる
3.2. 検索性・業務効率の大幅向上
紙の書類では、目的の請求書を探すのに時間がかかることが一般的です。
しかし、電子化により検索機能が使えるため、必要なデータに瞬時にアクセスでき、業務のスピードが大きく向上します。
- ファイル検索が数秒で完了する
- 担当者の作業時間を短縮できる
- 拠点が分かれていてもデータ共有が容易になる
3.3. セキュリティ対策と内部統制強化
紙の請求書は、紛失・盗難・誤廃棄といったリスクがつきものです。
電子保存なら、アクセス権限の設定や操作履歴の記録が可能で、セキュリティレベルを大幅に高めることができます。
- アクセス制限や操作ログの記録で不正を防止できる
- 紛失・盗難・誤廃棄のリスクが軽減できる
- 監査やコンプライアンス対応の精度が向上する
3.4. テレワークやBCP(事業継続)への対応強化
パンデミックや災害など、予期せぬ事態への備えとしても、ペーパーレス化は効果的です。
インターネット環境さえあれば、どこからでも請求書の確認や処理ができる体制は、テレワークやBCPの観点からも有用です。
- 出社せずに請求書業務が可能になる
- 災害時にも継続的な業務運用ができる
- 柔軟な働き方への環境整備に貢献できる
請求書のペーパーレス化は、単なる紙の削減にとどまらず、業務全体の効率化・可視化・リスク回避につながる重要な施策です。
法令対応と業務改善の両面からその導入価値は非常に高く、これからの業務の標準となっていくでしょう。
4. 請求書のペーパーレス化における重要なポイント

請求書のペーパーレス化を成功させるには、法令への対応だけでなく、実務運用やシステム面でも多角的な視点が求められます。
- 電子保存の要件を事前に正確に把握する
- スキャナ保存の技術要件と運用条件を確認する
- システム導入後の運用ルールを整備しておく
- インボイス制度との両立を前提にシステム設計する
- 宥恕措置の終了に伴う実務対応を完了させる
ここからは、スムーズな導入・定着のために押さえておきたい重要なポイントを解説します。
4.1. 電子保存の要件を事前に正確に把握する
電子帳簿保存法に則った保存を行うためには、法律で定められた保存要件(真実性・可視性)を正しく理解しておく必要があります。
- タイムスタンプの要
- 検索機能の実装範囲
- 操作ログの記録方法
- 書類の閲覧体制
誤解や見落としによって要件を満たさなかった場合、法的なリスクが発生するおそれがあるため、要件の確認は導入初期の最重要項目です。
4.2. スキャナ保存の技術要件と運用条件を確認する
紙の請求書をスキャンして電子保存する際は、一定の条件を満たしていなければなりません。
- スキャン直後の処理フロー
- 解像度(200dpi相当以上)と階調(グレースケール等)の確認
- 社内での定型ルールと運用手順の明文化
解像度や階調などの読み取り条件のほか、社内での承認プロセスやタイムスタンプの付与タイミングなども整理し、現場で対応できる体制を整えておきましょう。
4.3. システム導入後の運用ルールを整備しておく
どれだけ優れたシステムを導入しても、実際に現場で使いこなせなければ意味がありません。
- マニュアルや操作手順書の作成
- 承認フローの明文化
- トレーニング体制の整備
- 部署ごとの役割分担と責任範囲の明確化
運用ルールを文書化し、関係者間で共有することがペーパーレス化の定着につながります。
4.4. インボイス制度との両立を前提にシステム設計する
2023年からスタートしたインボイス制度(適格請求書保存方式)により、請求書の記載内容や保存義務が複雑化しています。
ペーパーレス化のシステムは、この制度に対応できる設計でなければ、運用に支障が出るおそれがあります。
- 適格請求書発行事業者番号の登録管理
- 税率ごとの区分記載対応
- インボイス対応のフォーマット出力
- 電子保存されたデータの検証機能
ペーパーレス化のシステムは、この制度に対応できる設計でなければ、運用に支障が出るおそれがあります。
4.5. 宥恕措置の終了に伴う実務対応を完了させる
2023年末をもって、宥恕措置(猶予期間)が終了したことにより、すべての企業は正規の保存要件を満たす体制に移行していなければなりません。
今からでも遅くはないため、未対応の部分があれば優先的に見直しましょう。
- タイムスタンプ運用の有無確認
- 事務処理規程の作成・社内共有
- 電子保存の検索機能の整備
- 税務署からの問い合わせに備えた証跡管理
未対応の部分があれば優先的に見直しましょう。
5. 請求書のペーパーレス化に対応するシステムの種類
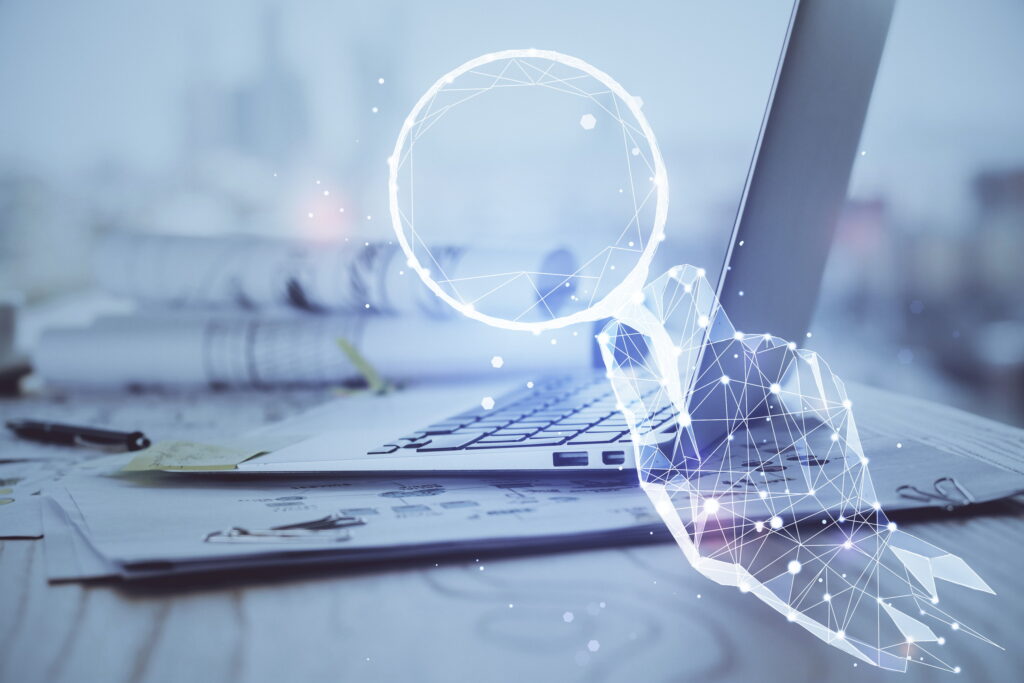
請求書のペーパーレス化を実現するには、用途や規模に応じた最適なシステムの選定が不可欠です。
- パッケージ型請求書管理システム
- カスタマイズ可能な業務特化型システム
- ERP(基幹システム)連携型請求書管理
- 自社開発型システム
- クラウド型請求書電子保存サービス
ここからは、主なシステムの種類とその特徴、活用されるシーンを具体例とともに紹介します。
5.1. パッケージ型請求書管理システム
既製品として提供される請求書管理システムで、インストール後すぐに利用できるのが特徴です。
基本的な請求業務に対応しており、設定も比較的簡単なため、初めてペーパーレス化に取り組む企業に適しています。
- 導入が容易で短期間で利用可できる
- 費用が比較的安価で済む
- 中小企業で紙の請求書管理に限界を感じている場合
- 社内で簡易的に電子保存を始めたい場合
5.2. カスタマイズ可能な業務特化型システム
業種や業務フローに特化したシステムで、自社の運用に合わせて柔軟に設計・構築できます。
建設業や医療業など、独自の帳票処理が必要な現場でも対応可能です。
- 業界特有の帳票やフローに対応できる
- 専用機能やインターフェースを柔軟に構築できる
- 請求フローが複雑で、汎用的なシステムでは対応できない場合
- 特定の帳票レイアウトや承認フローが必須の場合
5.3. ERP(基幹システム)連携型請求書管理
既に導入済みのERPシステムと連携する形で、請求書の管理機能を統合的に扱えるソリューションです。
財務・販売・仕入などの情報と一体化することで、企業全体のデータ活用が進みます。
- 業務全体の統合と情報の一元管理が可できる
- 分散していた処理を効率化し、ミスを削減できる
- 大企業や複数部門の業務を統合管理している場合
- 経理部門だけでなく、営業・仕入れ部門とも連携が必要な場合
5.4. 自社開発型システム
業務要件に完全にフィットさせるため、ゼロから開発する方式です。
外部システムとの連携、複雑な承認フロー、多言語対応など、要件が高度な場合に選ばれます。
- 要件に完全対応できる柔軟性と拡張性がある
- セキュリティ要件にも細かく対応できる
- 海外拠点を含むグループ会社で統一した請求管理が必要な場合
- 情報漏洩リスクを極力避けるため、自社サーバー上で完結させたい場合
5.5. クラウド型請求書電子保存サービス
インターネット経由で利用できるクラウドサービス型のシステムです。
初期費用が抑えられ、インフラ構築不要で手軽にスタートできます。
法改正へのアップデート対応も自動で行われることが多く、使いやすさが人気です。
- 初期導入が容易で月額制が中心
- 常に最新の法対応にアップデートされる
- 社内にシステム担当者がいない場合
- リモートワークを前提にした業務体制を整えたい場合
請求書のペーパーレス化を進める上では、単に「電子化できる」だけでなく、自社の業務フローや成長段階にマッチしたシステム選定がカギとなります。
目的や業務範囲に応じた適切な選択が、法令対応だけでなく、業務効率や企業競争力の向上につながる重要なステップとなります。
自社に最適なシステムを選定する際には、システム開発会社に相談することをおすすめします。
株式会社ブリエでは無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
6. 請求書のペーパーレス化のためのシステム導入のステップ
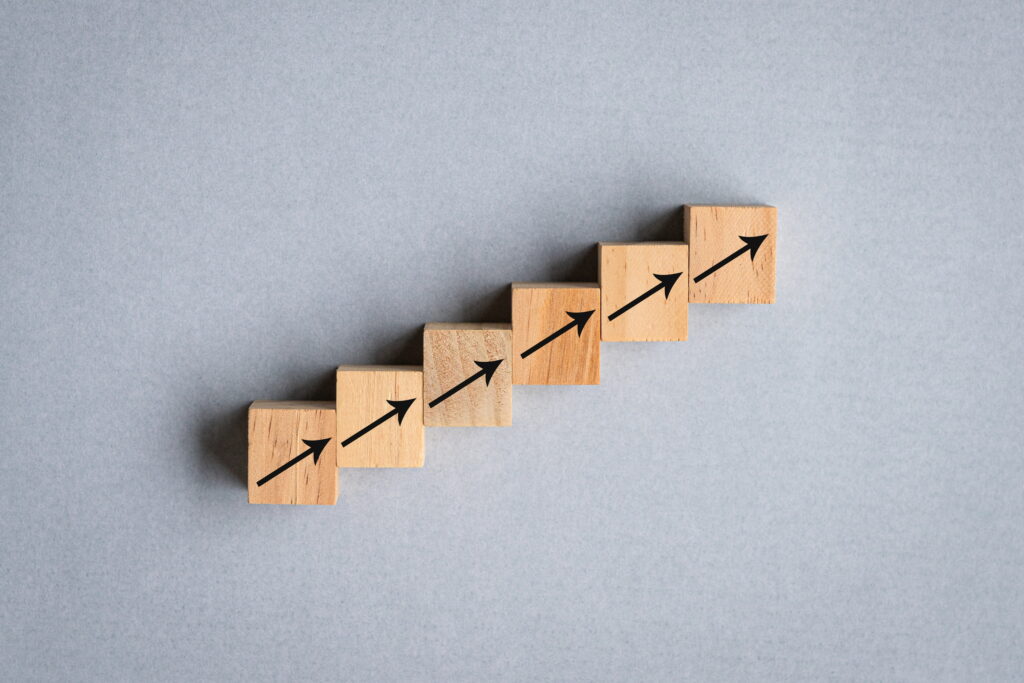
請求書のペーパーレス化を実現するためには、段階的な導入ステップを踏むことが重要です。
- 現状業務の棚卸し
- フローの可視化
- 要件定義
- システム開発会社の選定
- 試験運用
- 従業員トレーニング
- 運用ルールの策定
この章では、導入の流れと各ステップで意識すべきポイントについて解説します。
6.1. 現状業務の棚卸し
まず行うべきなのは、現在の請求書処理業務の棚卸しです。
紙での運用がどのように行われているか、誰がどのような作業をしているかを明確にし、業務の全体像を把握することで、ペーパーレス化における課題や改善点を洗い出せます。
- 請求書の発行〜保管までの一連の流れを図示する
- 業務の属人化や非効率なプロセスを明確にする
- 二重処理や手作業の有無をチェックする
- 紙ベースでの課題を洗い出す
6.2. フローの可視化
業務の棚卸しを踏まえて、各プロセスをフローチャートなどで「見える化」します。
これにより、どの部分に電子化の効果が高いか、また改善すべきボトルネックがどこかを判断しやすくなります。
- フロー図や業務一覧で課題箇所を可視化する
- 現場の声をヒアリングして実態を反映する
- 並行作業や手戻りが発生している部分を特定する
- システム化すべき範囲を事前に整理する
6.3. 要件定義
導入するシステムに求める機能や要件を明確にするフェーズです。
請求書の形式、保存期間、インボイス制度との連携、承認フロー、セキュリティ対応など、必要事項を洗い出しておくことが後のトラブル回避につながります
- 電子帳簿保存法に準拠した保存機能があるか確認する
- 今後の拡張性や法改正対応も見据えて検討する
- 自社の承認フローや運用スタイルに合うか確認する
- インボイス制度や取引先の仕様への対応力を確認する
6.4. システム開発会社の選定
定義した要件に基づいた適切な開発会社やパートナー企業選びは、システム導入に最も影響する要素です。
過去の導入実績や業界理解の深さ、サポート体制なども選定の判断材料となります。
- 自社と同じ業種・規模での導入事例があるか確認する
- 契約内容に保守運用や法改正対応が含まれるかを確認する
- 導入後のサポート体制やトラブル対応スピードを確認する
- UI/UXの使いやすさや実際の操作デモを確認する
6.5. 試験運用
本格導入前に、テスト環境で実際にシステムを運用してみます。
想定外のエラーや操作性の課題を事前に把握したり、改善したしたりすることができます。
- 現場メンバーに実際の処理を体験させてフィードバックを得る
- 法的要件を満たす帳票やログ管理ができているか検証する
- 処理スピードやエラー発生頻度をチェックする
- 想定される例外処理(再発行・取消など)も試す
6.6. 従業員トレーニング
新システムを効果的に活用するためには、利用者のスキル向上が不可欠です。
マニュアルの整備や説明会を実施し、定着を図ります。
- 役職別・部門別にカスタマイズしたトレーニングを実施
- 操作マニュアル・FAQを社内共有フォルダなどで展開
- 操作ミスが起こりやすい部分を事前に教育
- トレーニング後のアンケートで理解度を可視
6.7. 運用ルールの策定
システム導入後の継続運用を安定させるために、社内ルールやガイドラインを明文化します。
誰がどの業務を担当し、いつ・どこに保存するかを統一することが大切です。
- 業務分担や承認権限、保存ルールなどを明確に記載
- 定期的な運用レビューの仕組みも構築しておく
- 社内FAQや問い合わせフローも整備
- トラブル時のエスカレーションルートを明記
システム導入を成功させるには、段階的かつ丁寧なステップを踏むことが不可欠です。
現状分析からフロー可視化、要件定義、システム選定、トレーニングや運用ルールの整備に至るまで、すべてのフェーズで実務目線の検討と現場との連携が求められます。
導入後の定着や活用度を高めるためにも、最初の計画段階でしっかりとした準備を進めることが重要です。
7. 請求書のペーパーレス化に最適なシステム開発会社選びのポイント

システムの導入が成功するかどうかは、開発・導入パートナーの選定に大きく左右されます。
- 改正電子帳簿保存法対応の実績
- 柔軟なカスタマイズ性
- サポート体制とトラブル時の対応力
- コストと導入後のランニング費用
- 導入実績と顧客の評価
ここからは、システム開発会社を選ぶ際に重視すべきポイントを詳しく解説します。
7.1. 改正電子帳簿保存法対応の実績
まず最も重要なのが、法改正に対応したシステムを構築・導入した実績の有無です。
電子帳簿保存法の要件を満たすシステムを構築できるかどうかは、信頼性の高い開発会社を選ぶ基準となります。

- 対応実績のある業界や業務内容が依頼したい内容とマッチしているか
- 電子取引やスキャナ保存、タイムスタンプなどの要件に対応した開発経験があるか
- 実際の運用において法的要件を満たす運用サポートをしているか
- 改正内容のアップデートに継続的に対応しているか
7.2. 柔軟なカスタマイズ性
企業ごとに業務フローや帳票形式は異なるため、テンプレート対応だけでなく柔軟なカスタマイズが可能な開発会社を選ぶことが重要です。

- ワークフロー、承認ルート、レイアウト変更などへの柔軟な対応力があるか
- 要望を丁寧にヒアリングし、開発に反映できる体制が整っているか
- 標準機能の範囲外でも柔軟に拡張できる体制があるか
- 中長期的な運用変更に対応可能な構成かどうか
7.3. サポート体制とトラブル時の対応力
システムは導入して終わりではなく、運用中のトラブルやアップデートにも継続的な対応が求められます。
サポート体制が整っているかは、長期運用において重要な視点です。

- 保守契約やサポート対応時間、問い合わせの方法が明確であるか
- トラブル時の初動対応が迅速かつ的確に行える体制かどうか
- サポート窓口の対応レベルや、多言語・多拠点対応が可能か
- 利用者向けのFAQやマニュアルなどの整備がされているか
7.4. コストと導入後のランニング費用
初期導入費用だけでなく、月額費用や保守費用、追加開発コストなども含めた総合的なコスト感を把握しておくことが重要です。

- 初期費用とランニングコストの内訳が明確か
- カスタマイズや改修が発生した際の費用が分かりやすいか
- トライアル利用や段階的な導入計画の相談が可能か
- オプション機能や将来的なバージョンアップにはどの程度の費用がかかる
7.5. 導入実績と顧客の評価
実績豊富な会社は、類似業種・業態への導入経験をもとに、適切な提案が可能です。
実際の利用企業からの評判も信頼の指標になります。

- 同業他社での導入実績があるか
- Webサイトやインタビュー記事などで具体的な成果事例が確認できるか
- 第三者評価(レビューサイト、比較サイト)の情報が豊富か
- 継続率や契約更新率などの定量的指標が公表されているか
- 既存顧客からの評価コメントやフィードバックを参照できるか
請求書のペーパーレス化を成功させるためには、機能や価格だけでなく、法対応・柔軟性・サポート体制・実績といった多角的な視点でシステム開発会社を選定することが重要です。
自社の業務や体制と合致するかを丁寧に見極めることで、長期的に活用できるシステム導入が実現できます。
8. 請求書のペーパーレス化を目指すなら「ブリエ」

請求書のペーパーレス化を進めたいけれど、「どのシステムを導入すべきかわからない」「現場の声を反映できる開発会社を探している」という企業も多いのではないでしょうか。
そんなお悩みを抱えている場合は、ぜひ「株式会社ブリエ」ご相談ください。
ブリエは、現場の実態に即した業務設計を得意とし、ヒアリングから運用まで伴走型でサポートしております。
業種特有のニーズや既存システムとの連携にも柔軟に対応できるカスタマイズ力を備えており、単なる「システム導入」にとどまらない、本質的な業務改善を実現させます。
- 丁寧な現場ヒアリングに基づいたシステム設計
- 電子帳簿保存法・インボイス制度に完全対応
- ワークフローや承認ルートの柔軟なカスタマイズ
- 導入後の運用サポートと法改正対応のフォロー体制
- 中小企業から大手企業まで多様な導入実績
ペーパーレス化に向けて、業務に根ざしたシステムを導入したいとお考えの場合は、お気軽にご相談ください。
9. まとめ
- 電子帳簿保存法の改正により紙保存が原則不可に
- インボイス制度により請求書の記載要件が厳格化
- 業務効率やコスト削減のニーズが高まっている
- 多拠点・リモートワーク化により電子化が必須に
- BCP(事業継続計画)対応としても有効
- 帳簿・書類・請求書などの電子保存が義務化された制度
- 電子取引のデータ保存は紙保存では認められない
- スキャナ保存・タイムスタンプ・訂正履歴などの技術要件が必要
- 違反時には税務調査での否認リスクもある
- 2022年1月から段階的に施行、猶予期間にも注意が必要
- 請求書の作成〜送付〜保存までの一元管理
- 承認フローの電子化による業務の迅速化
- 郵送費・紙代などの経費削減
- 検索性や再発行のしやすさによる業務効率化
- 保管スペースの削減によるオフィス最適化
- 既存業務との整合性をどう取るか
- 法対応の漏れによるリスク
- 従業員のITリテラシーへの不安
- カスタマイズ性と標準機能のバランス
- システム導入後のサポート体制の不透明さ
- 電子帳簿保存法・インボイス制度への対応実績
- 柔軟なカスタマイズが可能か
- サポートやトラブル対応が手厚いか
- 初期費用とランニングコストの明確性
- 導入実績や顧客評価の公開状況
請求書のペーパーレス化は、単なる業務改善にとどまらず、法令対応・コスト削減・組織全体の効率化にもつながる大きな変革です。
本記事が、貴社のペーパーレス化の検討や、システム導入の判断材料として少しでもお役に立てば幸いです。

株式会社ブリエ代表取締役。Webデザイン、WordPress、Elementor、DTPデザイン、カメラマンなどを経て、FileMakerエンジニアとなる。企業の経営課題であるDX化、業務効率化、ペーパーレス化、情報の一元管理など、ビジネスニーズの変化に合わせてFileMakerで業務システムを開発し、柔軟に拡張して解決いたします。





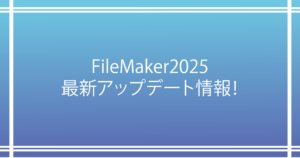




-1024x290.png)